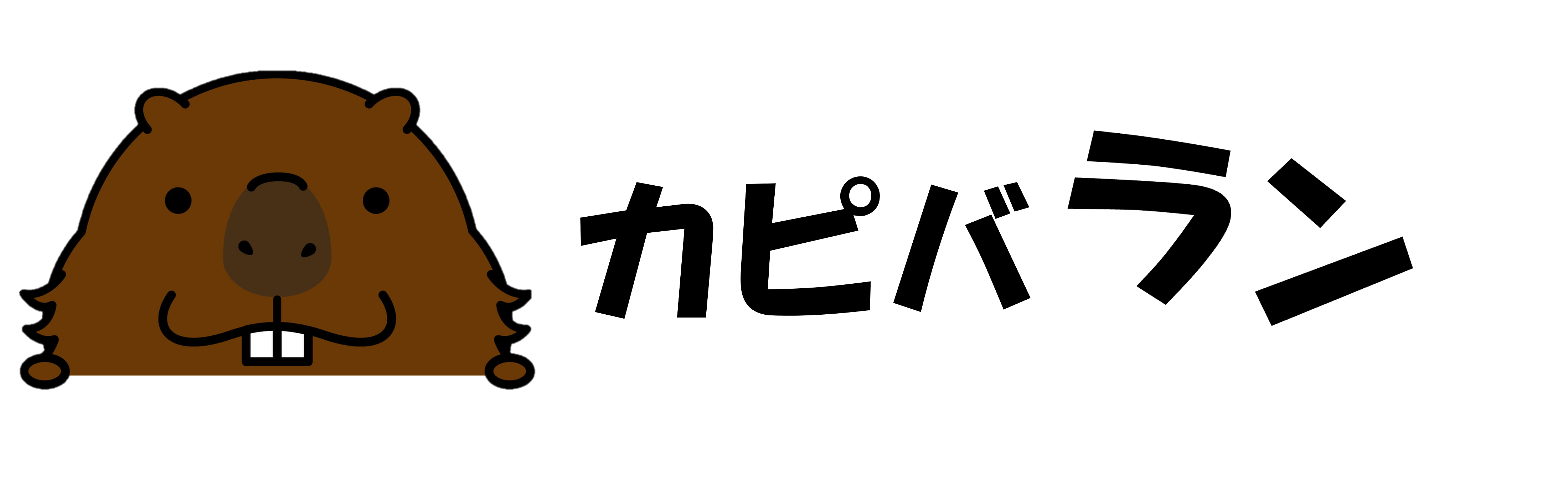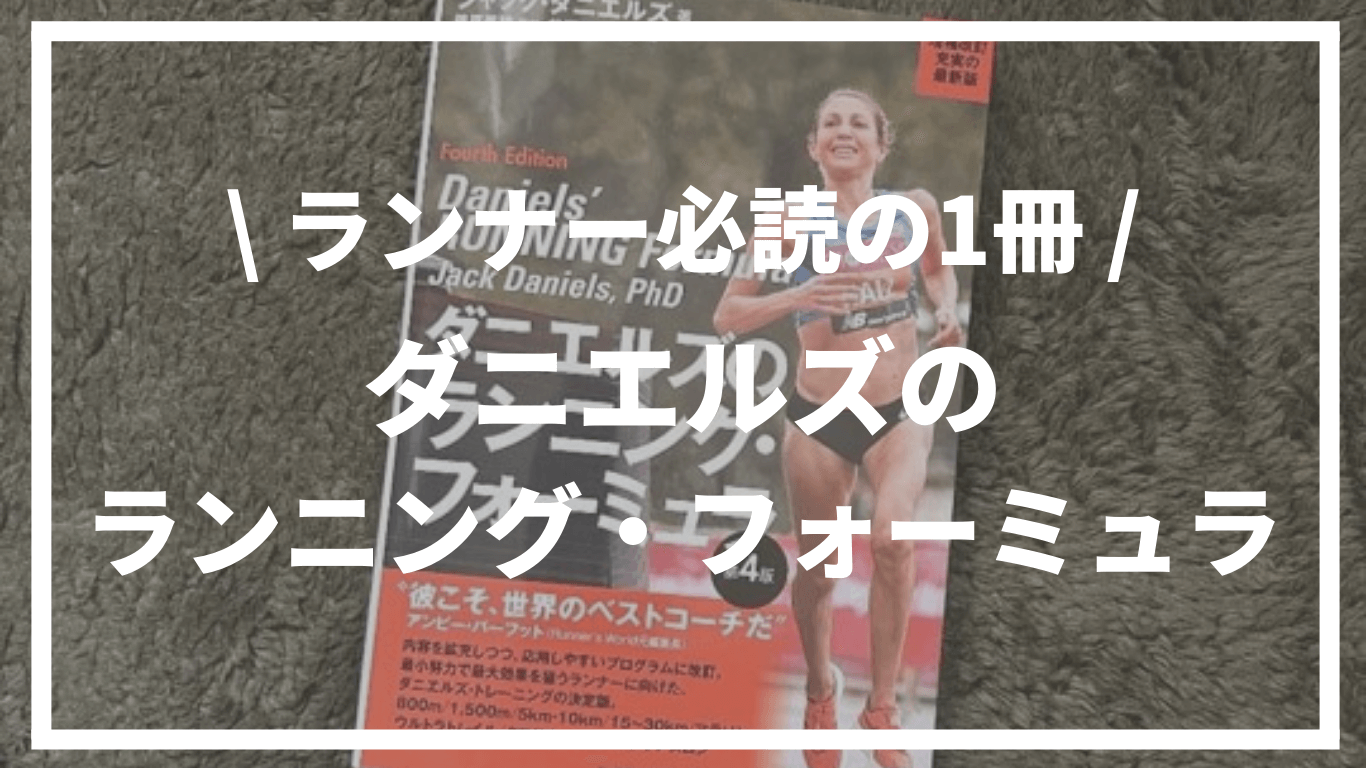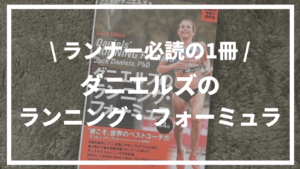N君
N君【ダニエルズのランニングフォーミュラ】という書籍が気になっています。購入する前に、どんな内容なのか概要について知りたいです。
こうした意見に答えます。
- 「ダニエルズのランニングフォーミュラ」概要
- ダニエルズ式トレーニングの特徴
本格的なマラソンシーズンに向けて、日頃からランニング・トレーニングに取り組んでいるという方も多いかと思います。
学生時代の部活動とちがって、「誰かに教えてもらいながら走っている」「チームに所属して複数人でメニューをこなしている」という方は少ないのではないでしょうか?
そんな時に役立つのが、トレーニング理論がまとめられた書籍です。。
数ある書籍の中でも世界的にベストセラーとなっているのが、今回紹介する【ダニエルズのランニングフォーミュラ】です。
こちらの書籍では、
- ランニングの基本原則
- トレーニングの原理
- 実際のトレーニングメニュー
といった感じで、理論~実践まで幅広く学ぶことができる一冊です。
要点をコンパクトに紹介していきますので、「購入前に概要を知っておきたい」という方は、ぜひ参考にしてください!

ブロックエディターに完全対応!
直感的な操作で簡単ブログ作成!
見るたび気分が上がるデザイン!
圧倒的な使い心地の最強テーマ!
圧倒的な使いやすさ、どんどん追加される新機能、おしゃれなデザイン性
そのすべてを兼ね備えた最強のWordPressテーマ「SWELL」
\ 国内最高峰の使い心地を手に入れよう /
「ダニエルズのランニングフォーミュラ」概要
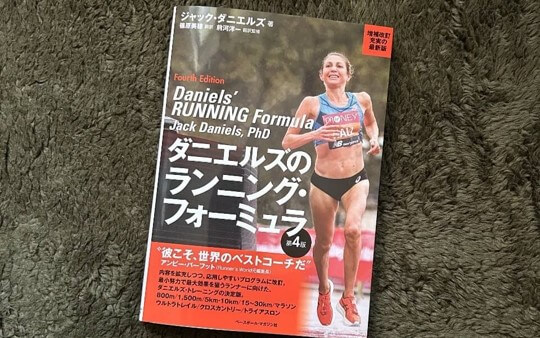
この書籍の著者は、「世界最高のランニングコーチ」と称されるジャック・ダニエルズ氏です。
学生を含む世界屈指の中・長距離選手を、コーチ・メンターとしてサポートし、そのキャリアは55年を超えます。
ダニエルズ氏自身も近代五種でオリンピックで2度のメダリスト、世界選手権では優勝を果たすなど、競技者としての実績も残されています。
そんな世界的なコーチの指導方法を学ぶことができるのが、「ダニエルズのランニングフォーミュラ」なのです。
書籍の構成
こちらの書籍は、以下のような項目で構成されています。
PARTⅠ フォーミュラを理解する
- 1章:ランニングの成功を決める要素
- 2章:トレーニングの原理とテクニックのポイント
- 3章:生理学的能力のプロフィールとトレーニングのプロフィール
- 4章:トレーニングのタイプと強度
- 5章:VDOT
- 6章:環境に応じたトレーニング・高地トレーニング
- 7章:トレッドミルトレーニング
- 8章:体力向上のトレーニング
- 9章:休養と補助的トレーニング
PARTⅡ フォーミュラを応用する
- 10章:1シーズンの構築
- 11章:800mのトレーニング
- 12章:1500mから2マイルまでのトレーニング
- 13章:5kmと10kmのトレーニング
- 14章:クロスカントリーのトレーニング
- 15章:15kmから30kmまでのトレーニング
- 16章:マラソンのトレーニング
- 17章:ウルトラトレイルのトレーニング
- 18章:トライアスロンのトレーニング
この構成から分かるように、トレーニング理論~具体的なトレーニングプログラムといった実践的な内容まで、幅広く学ぶことができます。
マラソンだけをピックアップしているわけではなく、中距離種目やクロスカントリー、ウルトラマラソンやトライアスロンといった種目まで、多くのアスリートに役立つ内容となっています。
ダニエルズによるトレーニングの特徴

ダニエルズによるトレーニングの特徴として、以下の3つが挙げられます。
- トレーニング強度の分類
- VDOTを用いたトレーニング強度の設定
- 4つのフェーズによるトレーニングの組み立て
それぞれ順番に見ていきましょう
①:トレーニング強度の分類
書籍ではトレーニング強度を5つに分類し、練習メニューの大半はこれらから構成されていると述べています。
トレーニング強度の5つの分類
- E(Easy)ランニング
- M(Marathon)ランニング
- T(Threshold)ランニング
- I(Interval)ランニング
- R(Repetition)ランニング
 カピまる
カピまるトレーニング強度は、【E⇒M⇒T⇒I⇒R】の順に高くなっているよ!
各トレーニングの内容や目的については、以下のとおりです。
| 項目 | トレーニング強度 | 目的・効果 | 週間走行距離に対する練習量 |
|---|---|---|---|
| E | 59~74% | 心筋の強化 血管新生の促進 | 25~30% |
| M | 75~84% | ペースに慣れる | 15~20% |
| T | 85~88% | 持久力強化 | 10% |
| I | 95~100% | 有酸素性能力の向上 | 10km or 8%のどちらか少ない方 |
| R | 105~120% | 無酸素性能力の向上 ランニングエコノミー スピードの向上 | 8km or 5%のどちらか少ない方 |
この表から、以下の2点が大切であることが分かります。
- 練習の大部分はEペース(ジョギング)
- 特定の練習ばかり行うのは非効率的
【Eペース(ジョギング)+○○】といったように、強度の低いものと高いものを組み合わせてトレーニングを行うことが効果的だと言えます。
②:VDOTを用いたトレーニング強度の設定
VDOTは、ダニエルズ氏がオリジナルで考案したもののひとつです。
これは、
- VO2max
- 最大強度の速度におけるランニングエコノミー
- レースにおける距離別%VO2max
といったデータをもとに作成された、ランニングの実力を測る独自の指標です。
こちらのサイトから、実際にVDOTの数値をカンタンに算出できるので、試しにやってみましょう。
ちなみに、僕の記録から算出したものがコチラ↓
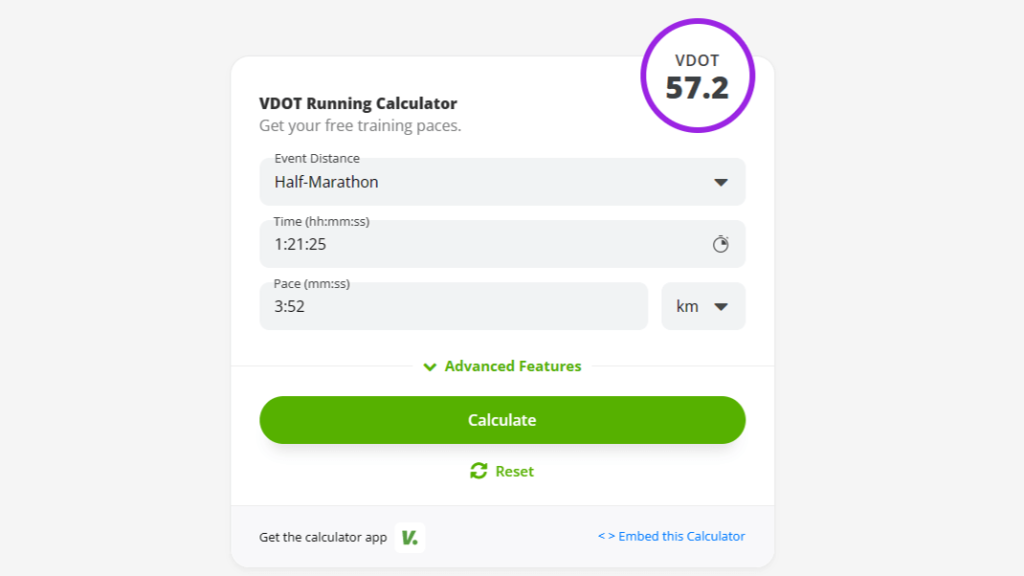
あわせてトレーニング強度(E,M,T,I,R)についても数値で示してくれるので、すぐにトレーニングに応用できて非常に便利です。
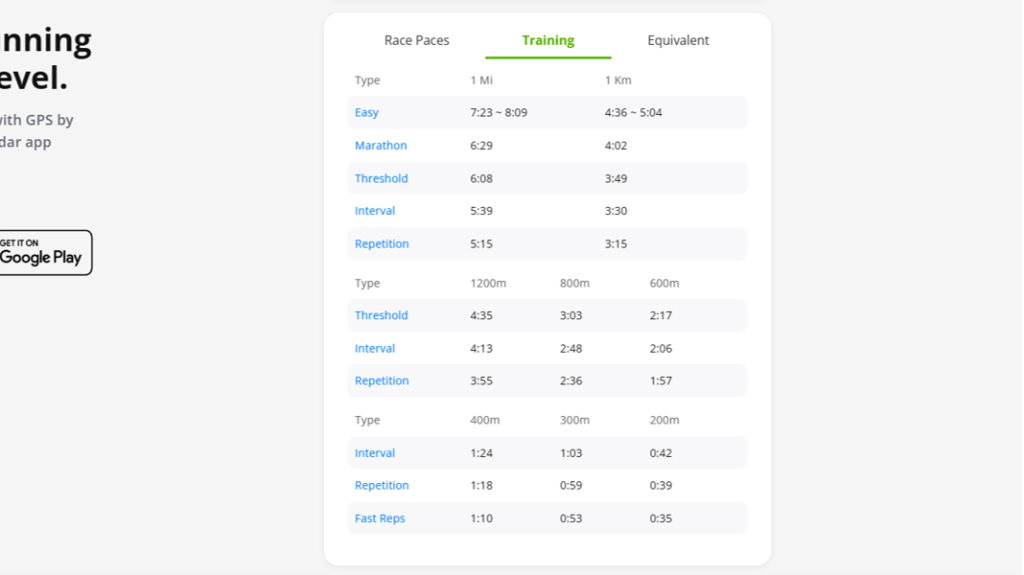
これを参考にメニューを考えれば、適度な負荷で効率よくトレーニングをこなすことが可能となります。
③:4つのフェーズによるトレーニングの組み立て
ダニエルズ氏によると、1シーズンを4つのフェーズに分けて考えることが大切だとしています。
| フェーズ | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| Ⅰ | 基礎トレーニング | 基盤の構築 ケガの予防 |
| Ⅱ | 質の高いトレーニングを行う はじめの段階 | 速いスピードへの適応 |
| Ⅲ | 質の高いトレーニングを行う 移行期の段階 | 有酸素性能力の向上 |
| Ⅳ | 質の高いトレーニングを行う さいごの段階 | 持久力の向上 スピードの強化 |
各フェーズの長さは、どの競技も同じというわけではありません。
- 中距離を走る⇒Rペースも積極的に行う。
- マラソンを走る⇒Iペースの頻度を増やす
といったように、自分が挑戦するレースに応じて設定することが大切だとしています。
こちらの書籍には、800m~トライアスロンまで、さまざまな種目におけるトレーニングメニューが掲載されています。
 カピまる
カピまるトレーニング内容を参考にしたい!という方は、一度読んでみる価値は十分にあると思うよ!
まとめ:「ダニエルズのランニングフォーミュラ」は必読です。
以上、「ダニエルズのランニングフォーミュラ」の概要について紹介しました。
- ランニングの基本原則
- トレーニングの原理
- 実際のトレーニングメニュー
といった内容について、これほど詳しく解説されている本は、他を探してもそうありません。
この記事では紹介しきれないほどボリューム満点な一冊なので、気になった方はぜひ一読してみてください!
 カピまる
カピまる【世界的なコーチの理論を学んで、トレーニングに活かしたい!】という方は、絶対に読むべきだと思うよ!
今回は以上です。最後までご覧いただき、ありがとうございました。