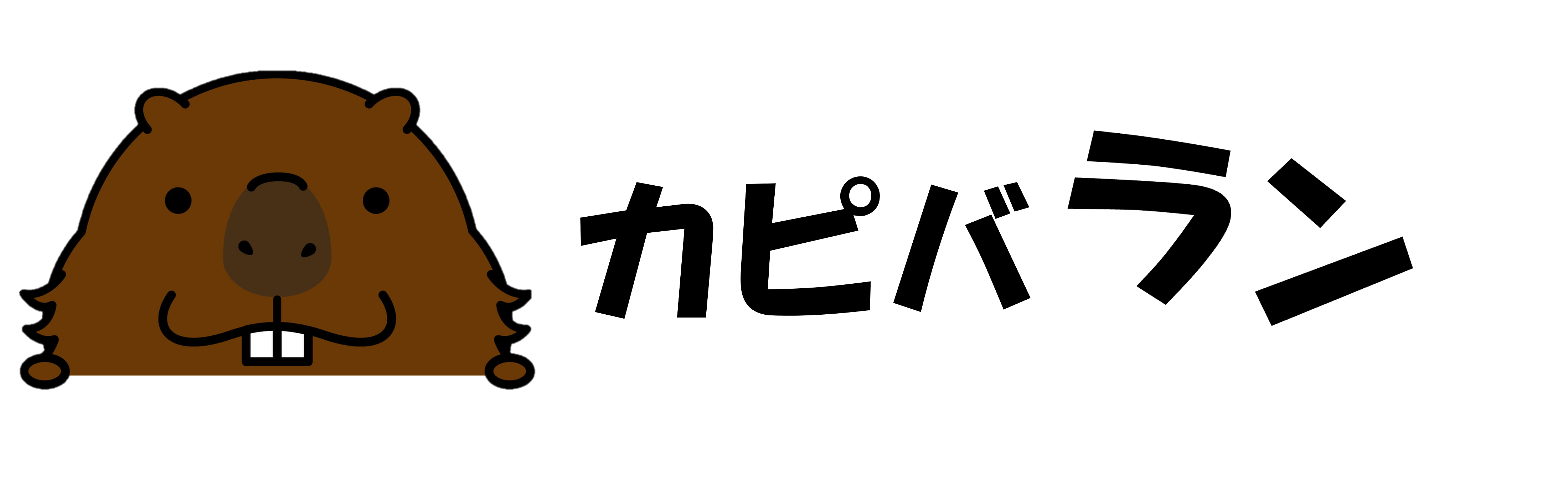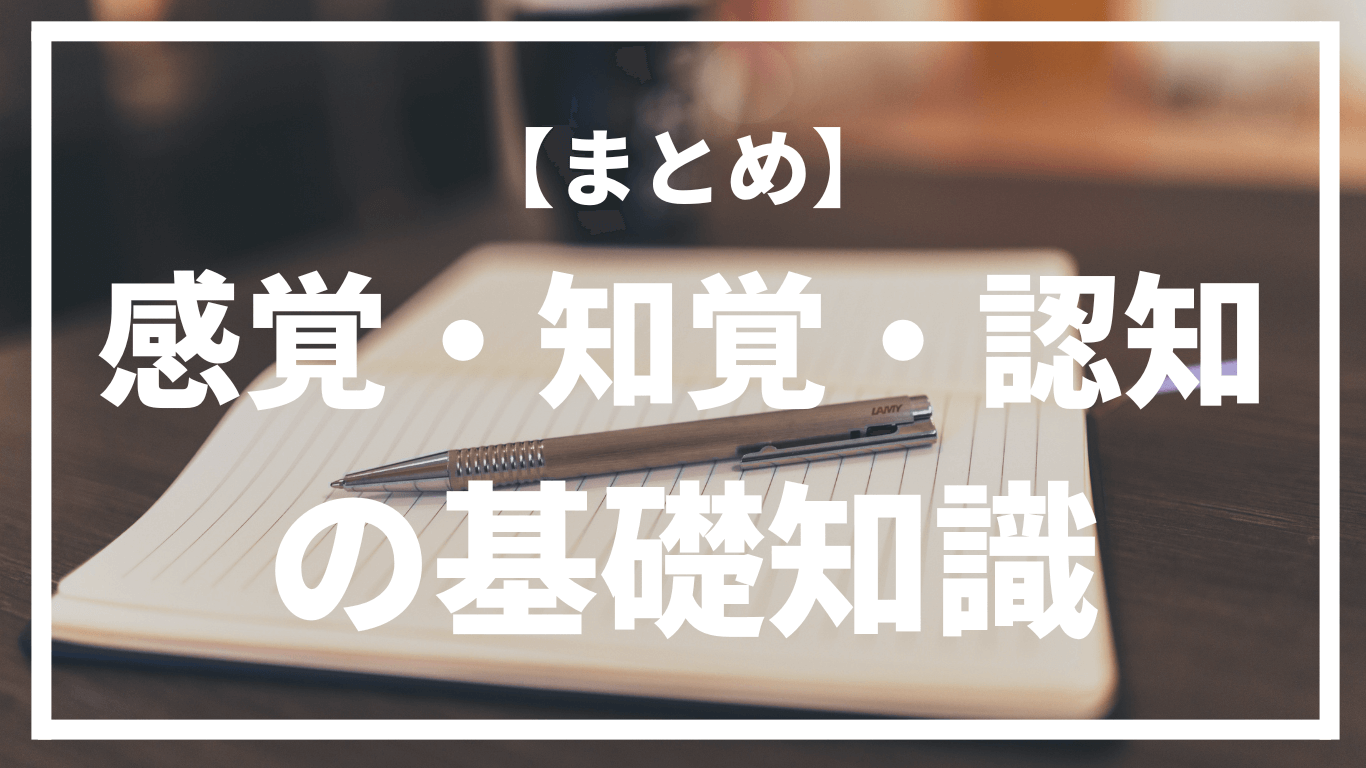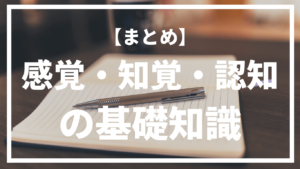N君
N君感覚・知覚のちがいって何だろう?分かりづらいよなぁ・・
 カピまる
カピまる似たような言葉で分かりづらいけど、しっかりと復習しておこう!
「感覚」「知覚」「認知」は、どれも同じ意味のように使われがちな言葉です。
日常生活はもちろん、医療や介護の分野で意味をまちがってしまうと、情報を正しく共有できなくなる恐れもあります。
そこで今回は、「感覚・知覚・認知の基礎知識」をテーマに、それぞれの用語について解説していきます。
本記事を一通り読めば、それぞれの言葉の概要について、十分理解していただけるはずです!
「感覚・知覚について理解が曖昧だなぁ…」という方は必見です。ぜひ最後までご覧ください!

ブロックエディターに完全対応!
直感的な操作で簡単ブログ作成!
見るたび気分が上がるデザイン!
圧倒的な使い心地の最強テーマ!
圧倒的な使いやすさ、どんどん追加される新機能、おしゃれなデザイン性
そのすべてを兼ね備えた最強のWordPressテーマ「SWELL」
\ 国内最高峰の使い心地を手に入れよう /
感覚・知覚・認知の基礎知識

早速ですが、「感覚」「知覚」「認知」の概要について、順番に解説していきます。
感覚の概要について
現在までに明らかになっている感覚については、以下表のとおりです。
| 種類 | 概要 | 感覚の例 |
|---|---|---|
| 体性感覚 | 皮膚感覚や深部感覚が含まれる。 受容器が身体全体に分布している。 | 触覚 痛覚 温度覚 運動覚 圧覚 振動覚 |
| 内臓感覚 | 内臓に分布した神経のこと。 内臓の状態を神経活動情報として感知する | 臓器感覚 内臓痛 |
| 特殊感覚 | いわゆるヒトの「五感」 受容器が特定部位に限られている | 視覚 聴覚 味覚 嗅覚 平衡覚 |
「感覚」は、「体性感覚」「内臓感覚」「特殊感覚」の3つに分類されます。
体性感覚の種類
体性感覚は、さらに「表在感覚」「深部感覚」「複合感覚」の3つの感覚に分類されます。
表在感覚…皮膚あるいは粘膜の感覚
- 触覚
- 痛覚
- 温度覚
深部感覚…骨膜、筋肉、関節等から伝えられる感覚
- 関節定位覚
- 振動覚
- 位置覚
- 運動覚
複合感覚…「知覚」を含む高次の感覚
- 二点識別覚
- 皮膚書字覚
- 立体認知
- 二点同時識別覚
内臓感覚の種類
内臓感覚は、内臓の状態を神経活動情報として感知する感覚です。
感覚の受容器(センサー)は、平滑筋・心筋・内臓粘膜に分布しています。
- 空腹感
- 食欲
- 口渇感
- 便意、尿意
- 性感覚
特殊感覚の種類
特殊感覚とは、いわゆる「五感」のことです。
感覚の受容器(センサー)が特定部位に限られているため、特殊な感覚として扱われています。
- 視覚
- 聴覚
- 味覚
- 嗅覚
- 平衡覚
知覚の概要について
「知覚」とは、「感覚」の性質・内容を識別したり、判断が加わったものとされています。
例えば、針で皮膚に触れた場合を考えてみると・・・
- 「感覚」=痛覚、触覚といった刺激の受容
- 「知覚」=痛みの強弱、針の太さ、表面の材質など
「感覚」と「知覚」には、このような違いがあります。
知覚の方が、感覚と比べて刺激の情報がより具体的になっていると言えます。
認知の概要について
「認知」は、知覚したものの情報処理過程のことを指します。
具体的には、
- 判断
- 解釈
- 推論
- 思考
- 記憶
- 課題の発見
などが挙げられます。
例えば、針で皮膚に触れた場合で考えてみると、「針は尖っていて、ヒトの身体には危険なもの。注意が必要」といったように、記憶の想起と行動を決定します。
「感覚」「知覚」のちがいは?

一般的な理解として、理論的に以下の階層構造を有しているされています。
感覚(sensation)⇒ 知覚(perception) ⇒ 認知(cognition)
ヒトが外部から刺激を受けると、受容器がそれを感じ取ります。
受容器から送られた感覚は、脳内で処理することで知覚され、さらに高次な情報処理によって認知・判断されます。
このように、「感覚」→「知覚」→「認知」と進むにつれて、外部からの刺激情報が段々と具体的になっていきます。
検査を行う意義

感覚・知覚検査を行う意義は、以下のとおりです。
- ADL動作障害を感覚・知覚機能の面から評価する
- 損傷部位、障害の範囲や程度を評価する
- 手の知覚機能の実用性を評価する
- 今後のリハビリテーション計画を立案する
リハビリテーションでは、日常生活活動(ADL)と退院後の社会生活を結びつけることが大切です。
感覚・知覚検査は、ADLと社会生活を想定し治療計画を立案するうえで重要な指標となります。
そのため治療を行う前に、きちんとした検査を実施する必要があります。
最後に
本記事では、「感覚・知覚・認知の基礎知識」をテーマに解説しました。
「感覚」「知覚」「認知」は、どれも同じ意味のように使われがちな言葉ですが、臨床で関わることが多い分野でもあるので、正しく理解をしておくことが大切です。
今回ご紹介した概要についてご確認いただき、今後の生活に役立てていただければ幸いです。
今回は以上です。最後までご覧いただき、ありがとうございました。