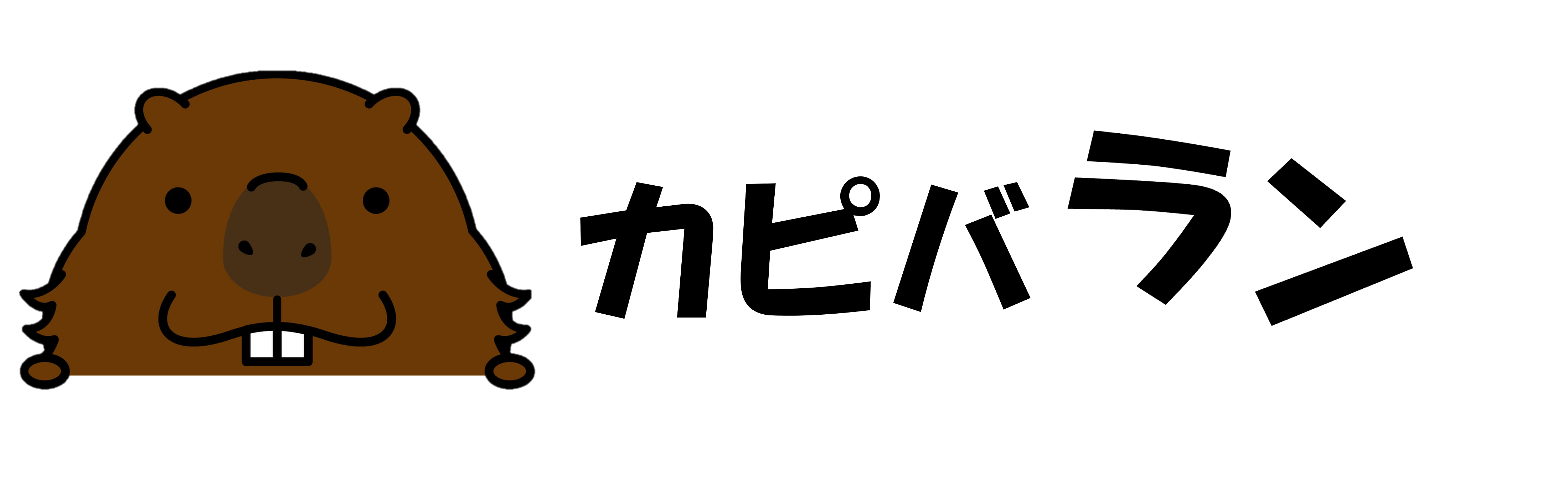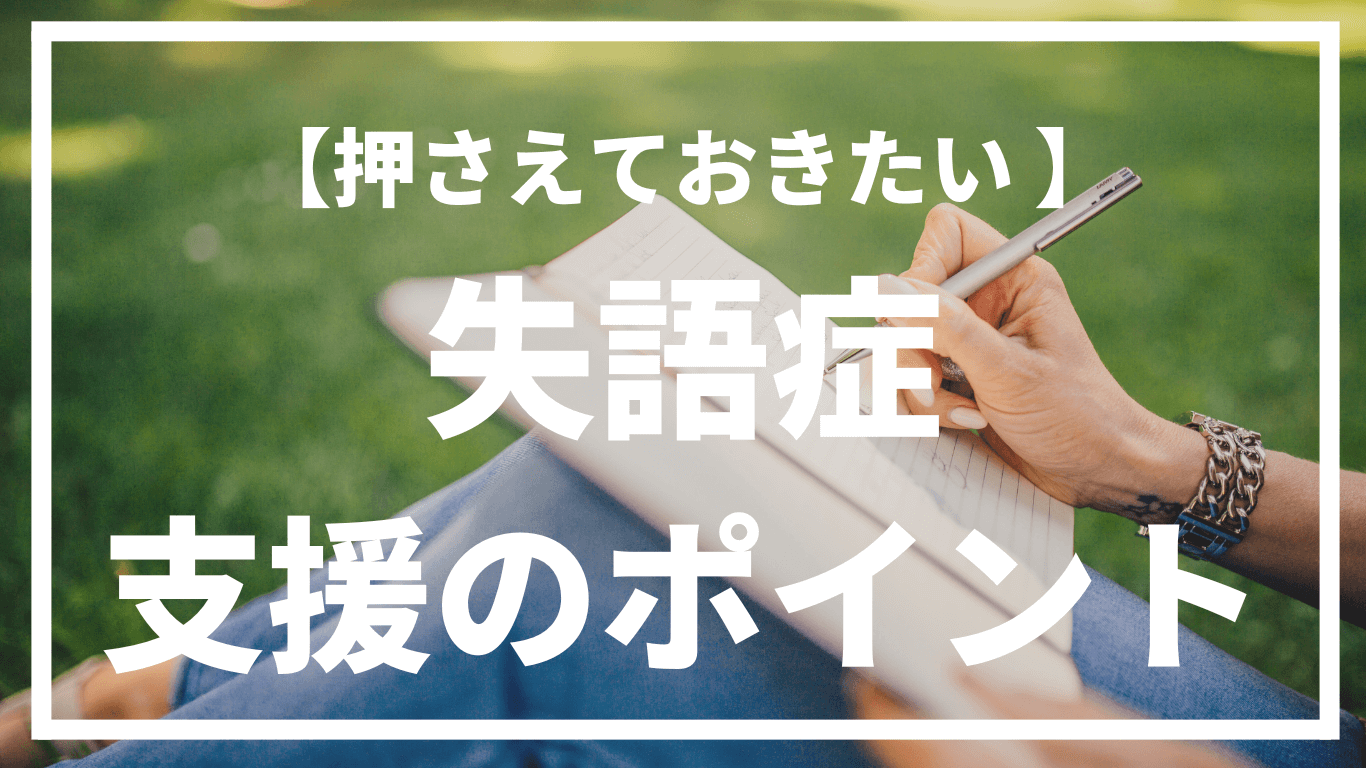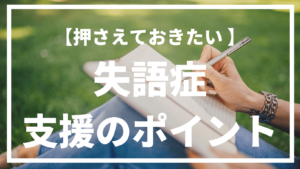N君
N君失語症の方との関わり方って、
どうするのが正解なんだろう?
 カピまる
カピまる失語症の方に対する支援方法として、
6つのポイントについて解説するよ!
失語症のようなコミュニケーション障害は、
- 自分の抱える思いを伝えられない
- してもらいたい、伝えたいことが伝わらない
- 相手の言葉が理解できない
といった精神的ストレスにつながり、リハビリテーションの妨げともなりうるものです。
その他にも、
- 本が読めない
- 字が書けない
といった活動にも影響を及ぼし、さまざまな生活場面での不自由さにつながります。
失語症の症状は、家族や周囲の方のサポートによって、少しずつ改善する可能性があります。
そこで今回は、「失語症の方に対する支援方法」をテーマに、関わる際のポイントについてご紹介します。
すぐにでも実践できる内容ばかりなので、ぜひ最後までご覧いただき、参考にしてください!

ブロックエディターに完全対応!
直感的な操作で簡単ブログ作成!
見るたび気分が上がるデザイン!
圧倒的な使い心地の最強テーマ!
圧倒的な使いやすさ、どんどん追加される新機能、おしゃれなデザイン性
そのすべてを兼ね備えた最強のWordPressテーマ「SWELL」
\ 国内最高峰の使い心地を手に入れよう /
基本的な接し方のポイント

失語症の方との基本的な接し方のポイントは、以下のとおりです。
- 「ゆっくり」「短く」「分かりやすく」
- 「はい」「いいえ」で答えられる質問をする
- 話題を急に変えない
- 分かりにくい内容は、くり返し伝える
- 正しく理解できているか、確認しながら話す
- 絵や写真、ジェスチャーを交える
- 実物を見せたり、その場に行って話をする
失語症の特徴として、
- 話す
- 聞く
- 読む
- 書く
といった、4つの言語的側面に障害が見られることがあります。
そして「言葉の意味」「文法」「音韻」「語彙」、それぞれの側面が障害されます。
こうした苦手とするコミュニケーションの側面を知り、相手が理解しやすくなるよう工夫をすることが重要です。
特に押さえておきたいポイントは、以下の3点です。
『ゆっくり、短い言葉で、はっきりと』が大原則!
相手が理解しやすくなるようなコミュニケーションは、
- ゆっくりと
- 短い言葉で
- はっきりと
話すことがとても重要であり、効果的であると言えます。
普段と同じような話し方ではなく、相手に理解してもらえるよう工夫するよう心がけましょう。
別の話題に触れる際には、事前にそのように伝えることで、相手に伝わりやすくなるはずです。
絵や写真、ジェスチャーを使う!
失語症の方は、「聞く」より「文字を理解する」ことが得意なことが多いです。
そのため絵や写真、ジェスチャーを用いたコミュニケーションがとても効果的です。
特定の話題について話す際には、キーワードを示しながら話すのも良いかもしれません。
「はい」「いいえ」で答えられる質問を!
失語症の方の場合、自分の思ったように言葉が出ないことがあります。
そのような時には、「はい」「いいえ」で答えられる質問をしましょう。
会話をする際には、相手が言いたいであろう言葉を推測し、質問することが大切です。
症状に合わせた接し方のポイント

ここでいう「症状」とは、以下のようなことを指します。
- 言いたい言葉が見つからない
- 言いたい言葉と違う言葉が出てしまう
- 言葉を聞いて理解することが難しい
それぞれの症状における支援のポイントを、順番に解説していきます。
①:言いたい言葉が見つからない場合
このような場合における支援のポイントは、以下のとおりです。
- 先回りして言ってしまわない
- 相手の言葉をさえぎらない
- 「はい」「いいえ」で答えられる質問をする
- 表情やジェスチャーから、相手の意図を判断する
失語症の方は、健常者と比べてコミュニケーションに多くの時間がかかってしまいます。
相手の話を聞く姿勢(=傾聴)を基本として、相手の言葉に寄り添うことが大切です。
なかなか言葉が出てこない時は、質問方法を変えてみましょう。
そうすることで、相手が少しでも答えやすいように工夫することが大切です。
②:言いたい言葉と違う言葉が出てしまう場合
このような場合における支援のポイントは、以下のとおりです。
- 一方的に相手の話を否定しない
- 伝えようとしている言葉を推測し、そのまま話を続けさせる
- 文字や絵で描き示しながら、内容を適宜確認する
感覚性失語(ウェルニッケ失語)のように、発話は流暢だけど錯誤が生じてしまうような方が該当します。
くり返しになりますが、大切なのは「傾聴の姿勢」です。
相手の伝えたいことを推測し、文字や絵を通して内容を確認しながら会話をしましょう。
③:言葉を聞いて理解することが難しい場合
このような場合における支援のポイントは、以下のとおりです。
- 短い言葉で、ゆっくりと話す
- 言葉の切れ目で少し間をおくよう
- 絵やジェスチャーを使用する
- 内容が伝わったかどうか、適宜確認する
普段の話し方以上に、ゆっくりと、短く分かりやすい言葉を使うことが大切です。
重要事項については、内容が伝わったかどうか、時々確認するようにしましょう。
主な注意点

失語症の方とコミュニケーションを取る際の注意点は、以下のとおりです。
- 子ども扱いをしない
- 一方的に否定しない
- 分かったふりをしない
この中でも特に注意が必要なのは、「子ども扱いしないこと」です。
注意点①:子ども扱いしない!
失語症の方とコミュニケーションを取る際のポイントとして、
- 「ゆっくり」「短く」「はっきり」話す
- 絵やジェスチャーを使う
- 「はい」「いいえ」で答えられる質問をする
といったことが重要だとお伝えしてきました。
これらは有効な手段ではありますが、やり過ぎてしまうと「子ども扱いされている」と不快感につながります。
相手のことを尊重する気持ちは忘れずに、適切な距離を保って関わるように心がけましょう。
注意点②:一方的に否定しない!
- 「それは○○じゃない。△△だよ~……」
- 「○○ってどういうこと?△△じゃないの~……」
一方的に話を否定されると、相手もコミュニケーションを取りたいと思いません。
「傾聴」の姿勢を基本として、相手の言葉に耳を傾けることが大切です。
その中で、「はい」「いいえ」で答えられる簡単な質問を行い、話の内容を整理しましょう。
注意点③:分かったふりをしない!
分かったふりをしていると、相手も伝わっていると思い、どんどん話を進めようとします。
それなのに伝わっていないとなると、混乱をまねきコミュニケーションに支障が出ます。
お互いに情報を共有しているという意識を持つことが大切です。
さいごに
今回は、「失語症の方に対する支援方法」をテーマに、関わる際のポイントについて解説しました。
正しい知識を持って対象者の方と関わり、支援を行うように意識していきましょう。
すぐに実践できる内容ばかりですので、ぜひ今後の生活に役立ててください。
以下の記事では、失語症の概要について詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
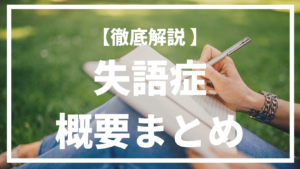
今回は以上です。最後までご覧いただき、ありがとうございました。