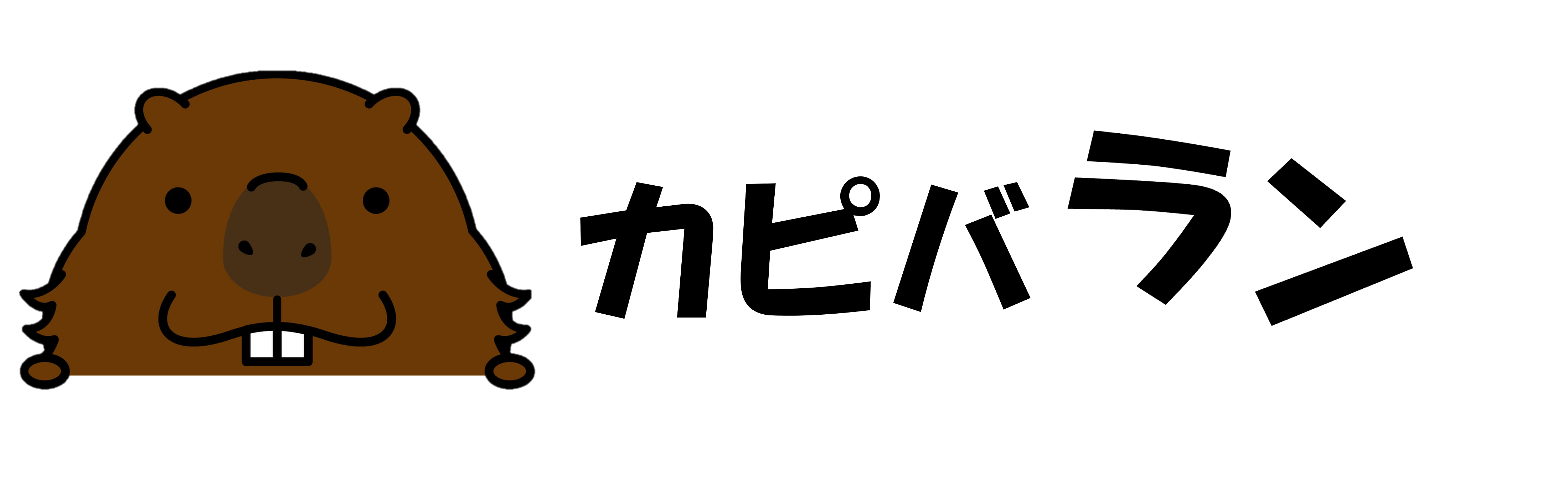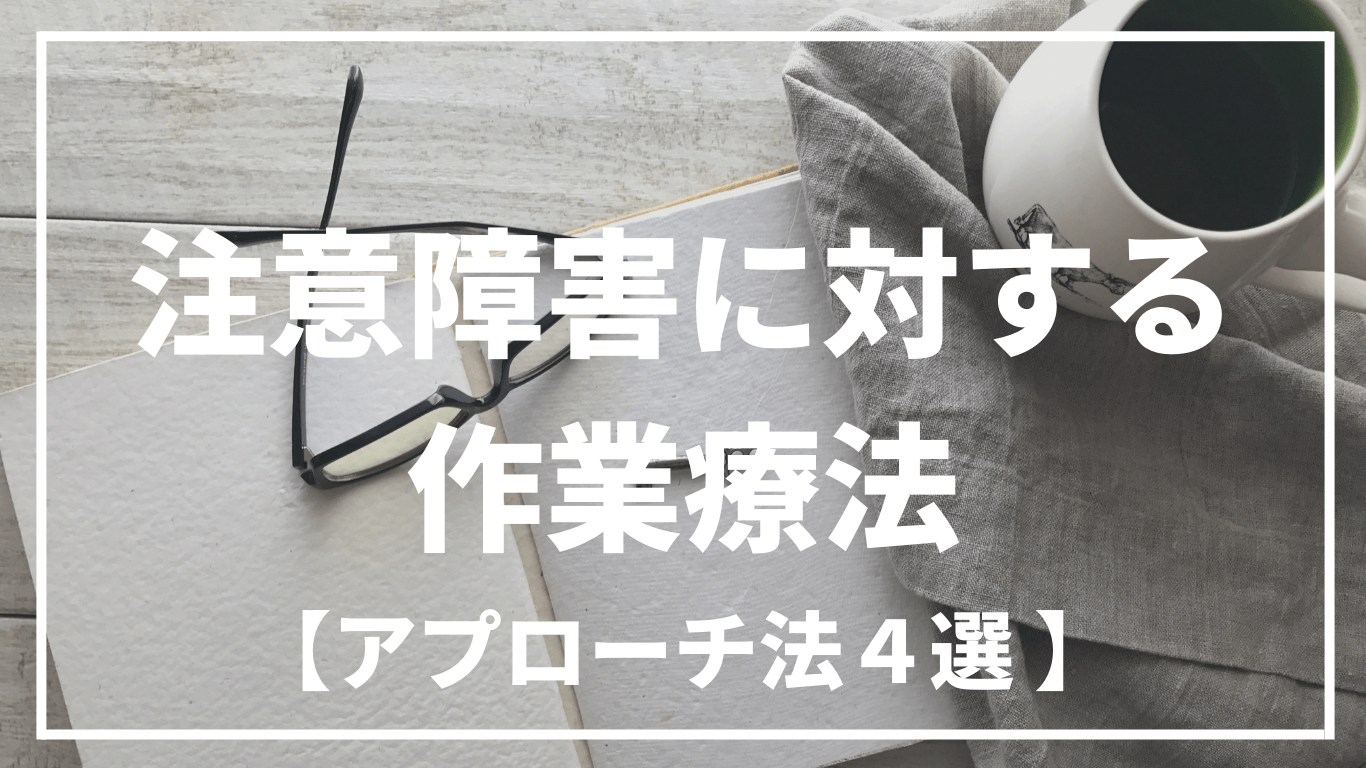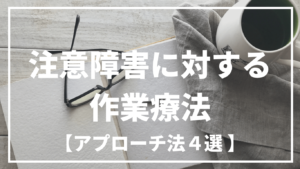N君
N君注意障害に対するリハビリテーションについて、どのような視点で介入すべきか、ポイントがあれば教えてほしいです。
注意障害では、
- 作業中にミスしやすくなる
- 同時に複数の仕事をこなせない
- 集中力が続かない
といった症状がみられ、日常生活を送るうえで大きな影響を及ぼします。
自立した生活を送れるよう支援を行うためには、注意障害に対する適切なアプローチ方法を知ることが大切です。
そこで今回は、『注意障害に対する作業療法』をテーマに、4つのアプローチ方法について解説していきます。
- 具体的なアプローチ方法を知りたい!
- 注意障害の方と接する際の注意点等について学びたい!
上記のような方は、ぜひ参考にしていただき、今後の生活に役立てていただければ幸いです。

ブロックエディターに完全対応!
直感的な操作で簡単ブログ作成!
見るたび気分が上がるデザイン!
圧倒的な使い心地の最強テーマ!
圧倒的な使いやすさ、どんどん追加される新機能、おしゃれなデザイン性
そのすべてを兼ね備えた最強のWordPressテーマ「SWELL」
\ 国内最高峰の使い心地を手に入れよう /
注意障害に対する4つアプローチ方法

今回ご紹介する『注意障害に対するアプローチ』は、以下の4つです。
- 全般的アプローチ
- 特異的アプローチ
- 動作課題
- 環境調整
それぞれについて、順番に解説していきます。
方法①:全般的アプローチ
注意機能全般に対するアプローチの目標は、課題に集中できる作業時間を延ばし、ミスを1つでも減らすことです。
難易度設定には注意し、取り組みやすい課題からはじめて徐々に難しくしていきます。
使用する課題は、パズルやボードゲーム、計算ドリルといった身近なもので構いません。
完成度が目に見えて分かり、課題に取り組む中で達成感が得られやすいものがお薦めです。
方法②:特異的アプローチ
特異的アプローチ手法の1つとして、ATP(Attention Process Training )があります。
ATPは、個々の注意障害に対して個々の課題を実施しながら注意機能全体の改善を目標としたプログラムです。
訓練として、以下の項目が含まれます。
| 注意の種類 | 課題の内容 |
|---|---|
| 持続性注意 | 1.number cancellation(末梢課題:数字、図形) 2.attention tape(聴覚刺激を与え、ボタンで反応) 3.serial numbers(連続7減算、6減1増を繰り返す) |
| 選択性注意 | 1.shape cancellation with distractor overlay 2.number cancellation with distractor overlay 3.attention tape with background noise →視覚的・聴覚的妨害刺激を与えながら行う末梢課題 |
| 転換性注意 | 1.flexible shape cancellation 2.flexible number cancellation 3.odd and even number identification 4.addition subtraction flexiblity 5.set dependent activity →ターゲットを課題途中で変更させながら行う末梢課題 |
| 配分性注意 | 1.dual tape and cancellation task 2.card sort →テープを聞きながら末梢課題を行う(二重課題) |
- 持続性注意
- 選択性注意
- 転換性注意
- 配分性注意
という、注意の4特性ごとに障害の程度を評価します。
そして、正答率が50%前後の課題を選択し、訓練課題として使用します。
訓練は1週間に4~5セッション、4~10週間行います。
同じ課題をくり返し行いながら、徐々に難しい課題へと移行していきます。
方法③:動作課題
ADLやIADLの練習では、動作の目標を対象者の方と一緒に設定します。
そして、段階付けを行いながら、くり返し練習を行います。
段階付けの例
 N君
N君車いすからベッドに自力で移れるようになりたい!
対象者の方のこうした希望をもとに、課題に取り組むうえでの目標を設定したとします。
この目標に対する段階付けの例としては、以下のとおりです。
- 車いすをベッド横に着ける
- 両側のブレーキをしっかりかける
- フットレストから足を下ろす
- ベッド柵や車いすのアームレストをしっかり掴む
- しっかり立ち上がった後、方向転換をしてベッドに移る
最初は見守りつつ口頭指示で次の動作を確認しながら、安全に行うよう心がけましょう。
そしてある程度練習し慣れてきたら、徐々に口頭での指示を減らします。
対象者の方自身で行うことができるように、支援の仕方を変えることがポイントです。
また、課題への取り組みに対して適宜フィードバックを行い、集中して取り組めるように配慮することも大切です。
方法④:環境調整
注意障害がある方へのアプローチとして重要なのが、『環境調整』です。
これらは一般的に、
- 物理的環境調整
- 人的環境調整
の2つに分類されます。
物理的環境調整
- 静かな環境で1人で取り組めるように配慮する
- 騒音などの聴覚的妨害刺激も極力避けるようにする
- 障害物のないバリアフリーな環境に調整する
人的環境調整
- 周囲の方に障害による影響を説明し、理解を促す
- ご家族に対し、自主練習のサポート役を依頼する
- 部屋の整理整頓など、日常生活における支援・監督を依頼する
注意障害があると、転倒リスクがとても高まることが懸念されます。
高齢の方がいる場合、段差や通路のモノを少なくするといった環境調整が重要になります。
作業療法を行う上での大原則

注意障害に対する作業療法を実施する上での大原則は、以下のとおりです。
- しっかりと覚醒した状態の時にリハビリを行う
- 課題の難易度は、低いもの→高いものの順に行う
- 結果に対するフィードバックを適宜行う
原則①:しっかりと覚醒した状態の時にリハビリを行う
十分に覚醒していない場合、
- 課題に集中できない
- 過度に疲労を感じてしまう
といった状態に陥る可能性が高くなります。
 N君
N君眠たい時や疲れている時だよね!確かに集中しろと言われても難しいよ…。
何よりもまず初めに、課題を実施できる状態であるかどうか確認するようにしましょう。
原則②:課題の難易度は、低いもの→高いものの順に行う
課題を実施する順番にも、注意が必要です。
- 簡単すぎる問題が続く場合
- 難しすぎる問題が続く場合
こうした課題では、その方の機能を適切に評価することができません。
少しずつ難易度を上げていくことで、集中力を長時間保つことが可能となり、正しく評価することができます。
難しい課題ばかりくり返し行ってしまうと、
 カピまる
カピまる全然できなかった…自分はなんてダメな人間なんだろう…
このように、自己肯定感の低下にもつながってしまう恐れもあるため、気をつけましょう。
原則③:結果に対するフィードバックを適宜行う
- 間違いが何問も続いてしまっている場合
- 表情などに不安そうな感情が表れている場合
こうした時には、現在の状態を伝え、正しく修正することを促す必要があります。
声掛けによって一区切りしながら行った方が、高い集中力を保つことができるので、課題成績も良くなります。
 カピまる
カピまるフィードバックのし過ぎはNGだよ!
適切なタイミングで行うことが大切なんだ!
さいごに
今回は、『注意障害に対する作業療法』をテーマに、4つのアプローチ方法について解説しました。
自立した生活を送れるよう支援を行うためには、注意障害に対する適切なアプローチ方法を知ることが大切です。
本記事でご紹介した4つのアプローチ方法を、ぜひ参考にしてください!
以下の記事では、『注意障害に対する評価』について解説していますので、併せてご覧ください。

今回は以上です。最後までご覧いただき、ありがとうございました。