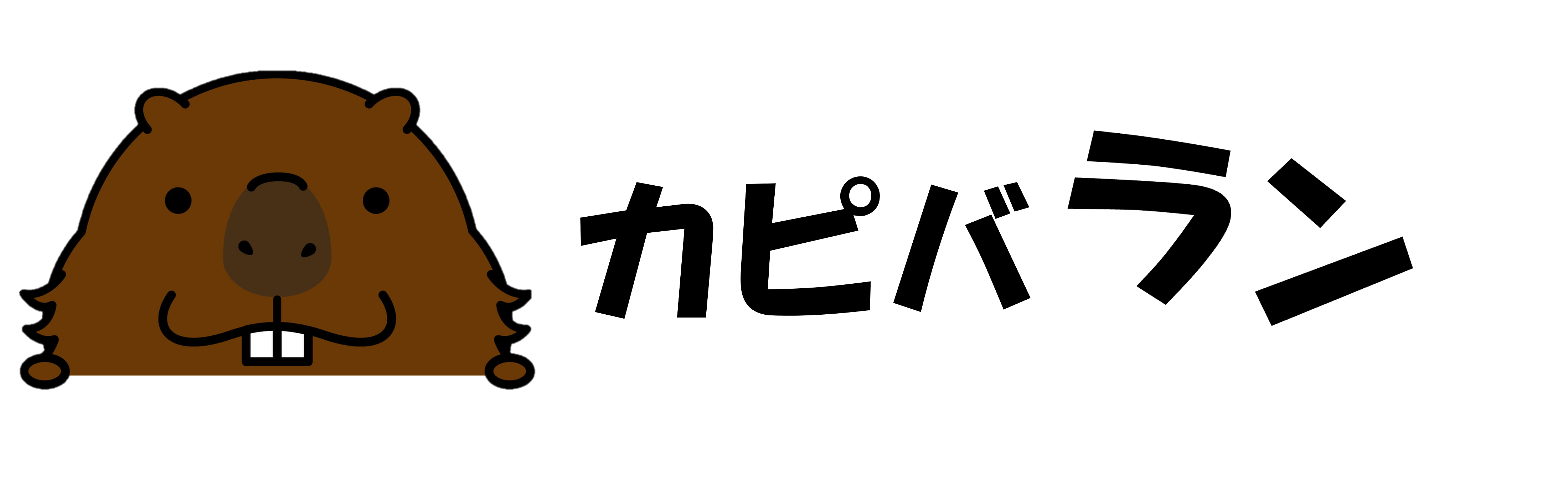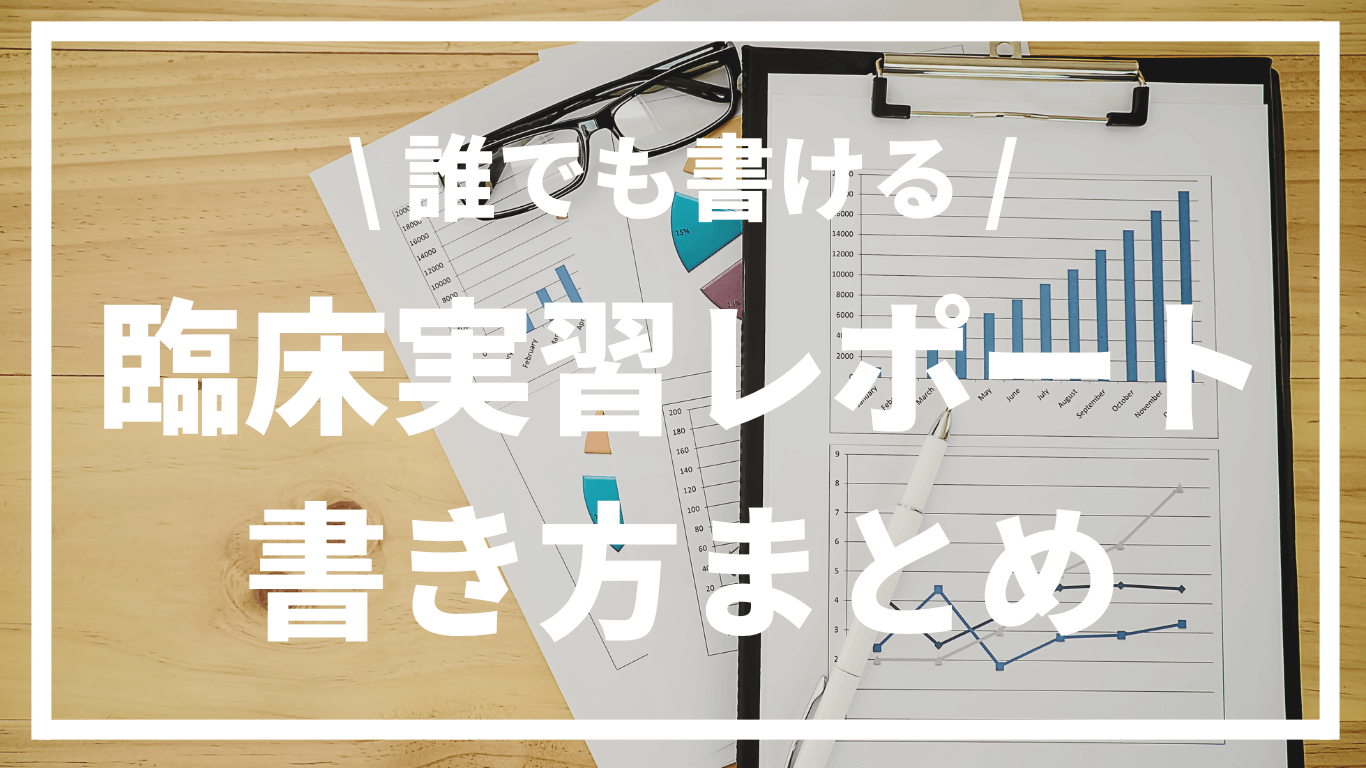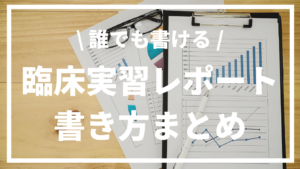N君
N君実習のレポートってどうやって書けば良いんだろう。上手くまとめられるか不安だなぁ。
こうした悩みに答えます。
- レポート作成のルール
- 記載すべき項目まとめ
作業療法臨床実習において、最も大きなウェイトを占めているのがレポート作成です。
実習に向けて専門知識や手技についてはたくさん学ぶ一方、レポートの書き方について学ぶ機会はほぼないのが現状です。
そのため、
- いざ書こうと思っても進まない・・
- 何から書けばいいか分からない・・
- 書くのに時間がかかってしまう・・
こうした状態に陥ってしまい、実習で苦しんでいる・・という方もいるかと思います。
そこで今回は、「作業療法臨床実習レポートの書き方」について、レポート作成のルールや記載すべき項目について詳しくまとめます。
本記事で紹介するポイントは、
- 臨床実習Ⅰ(基礎学実習)
- 臨床実習Ⅱ(評価学実習)
- 臨床実習Ⅲ(総合実習)
といった、あらゆる実習で活用できる内容となっています。
「これから実習を控えている」「レポートの書き方を知りたい」という方は、ぜひ参考にしてください。

ブロックエディターに完全対応!
直感的な操作で簡単ブログ作成!
見るたび気分が上がるデザイン!
圧倒的な使い心地の最強テーマ!
圧倒的な使いやすさ、どんどん追加される新機能、おしゃれなデザイン性
そのすべてを兼ね備えた最強のWordPressテーマ「SWELL」
\ 国内最高峰の使い心地を手に入れよう /
【はじめに】レポート作成時のルールを確認しよう

レポートを書き始める前に、まずは作成時のルールについて確認しておきましょう。
ルール①:書式について
レポートの書式に関するルールは、以下のとおりです。
- 用紙・・基本A4サイズ(場合によってはA3)
- 枚数・・特に決まりなし(多すぎはNG)
- 印刷・・片面・両面どちらでも可
レポートは、A4サイズで作成するのが一般的です。
症例報告を行う際など、場合によってはA3サイズで作成することもあります。
枚数について具体的な決まりはないですが、あまり多すぎると「まとまっていない」と判断されかねないので注意しましょう。
ルール②:記載方法について
次にレポートの記載方法に関するルールは、以下のとおりです。
- 字体・・MSゴシック、MS明朝
- 文体・・「である調」「ですます調」に統一する
- 文章・・主語と述語は明確に。一文が長くなり過ぎないように。
- 漢字・・常用漢字を使用する
- 仮名・・現代仮名遣いを使用する
- 句読点・・文全体を見て、バランスよく配置する
- 見出し・・大項目「Ⅰ、Ⅱ」中項目「(1)、(2)」小項目「a、b」など
この中で気を付ける必要があるのは、「文体」と「文章の長さ」です。
レポートは相手に読んでもらう必要があるので、「読みやすい」「理解しやすい」文章を書くことが大切です。
一文が長くなりそうなときは、以下のように
- 大項目→ローマ数字(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)
- 中項目→アラビア数字(1、2、3)
- 小項目→アラビア数字+カッコ書き((1)、(2)、(3))
- その他→アルファベット(a、b、c)や数字(①、②、③)
といった見出し表記で、小項目に分けて記載しましょう。
レポートに記載すべき項目一覧
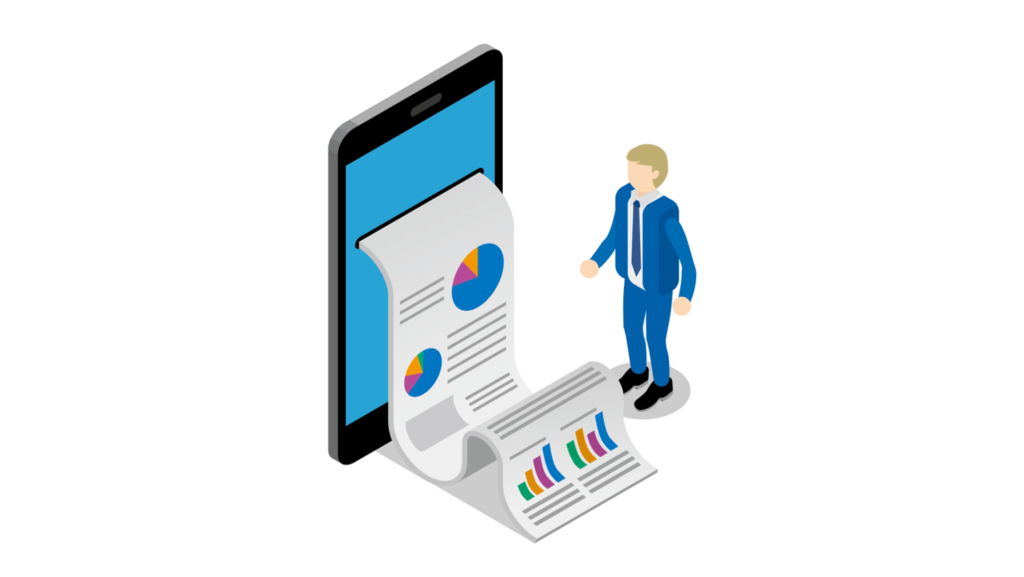
 N君
N君基本的なルールは理解できたけど、具体的にどうやって書けばいいんだ・・?
 カピまる
カピまる記載する項目は決まっているから、型(テンプレート)に沿って書くことが大切なんだ!
レポートを作成する際には、以下の項目に沿って書きすすめることが大切です。
- はじめに(タイトル+要約文)
- 症例プロフィール
- 医学的情報
- 社会的情報
- 他部門からの情報
- 作業療法評価
- ICFによる整理
- 統合と解釈
- 目標設定、治療計画立案
- 治療経過(中期評価、最終評価)
- 考察、まとめ
- 参考文献
各項目について、詳しく解説していきます。
項目①:はじめに(タイトル+要約文)
ここでは、『どのようなケースを報告しようとしているか』をまとめます。
レポート全体で言いたいこととして、タイトルと要約文を記載する必要があります。
具体的には、
- どのような障がいがあるか
- 病前の生活はどうだったか
- 何に対して介入を行ったか
といったことを踏まえながら、介入の目的や動機を簡潔にまとめます。
項目②:症例プロフィール
症例プロフィールでは、
- 氏名
- 性別
- 年齢
- 利き手
- 婚姻の有無
といった内容について記載します。
氏名は「伏せ字」もしくは「イニシャル表記」、年齢は『○○代』として具体的に書きすぎないよう配慮しましょう。
項目③:医学的情報
医学的情報では、
- 診断名
- 障がい名
- 合併症
- 現病歴
- 既往歴
といった内容について記載します。
症例プロフィールと同様に、「人物が特定されない」ように配慮することに注意しましょう。
ある時点(生まれた年など)をX年とし、「X+○○年」と表記しましょう。
障がい名などは略語を使わず、正式な医学用語で記載しましょう。
項目④:社会的情報
社会的情報では、
- 家族歴
- 家族構成
- キーパーソン
- 生活歴
- 家屋環境
- 経済状況
- 保険の有無
- その他(趣味・興味など)
といった内容について記載します。
こうした情報は、退院・転院を検討する際に必要な情報となります。
他職種の方も参考にする項目ですので、できるかぎり正確に記載しましょう。
項目⑤:他部門からの情報
他部門からの情報収集を行う際は、以下について確認しましょう。
- 医師→予後予測、リスク管理など
- 看護師→1日の生活状況
- 理学療法士→歩行機能
- 言語聴覚士→摂食・嚥下機能
- ソーシャルワーカー→今後の転院先など
必要な情報について、簡潔にまとめるように心がけましょう。
項目⑥:作業療法評価
カルテや他職種から情報収集を行い、必要な評価をピックアップして行います。
作業療法評価の例としては、
- 面接、観察、問診
- ROM
- MMT
- ブルンストローム
- 感覚検査
- 筋緊張検査
- 反射検査
- バイタルサインの測定方法
- 協調性検査
- 高次脳機能検査
- 上肢機能検査
- ADL評価
などが挙げられます。
評価によっては、負担が大きい評価も含まれるので必要なもののみ実施しましょう。
項目⑦:ICFによる情報整理
ICF(国際生活機能分類)とは、「生活機能と障害に関する分類法」のことです。
以下の図のように、
- 健康状態
- 心身機能・身体構造
- 活動
- 参加
- 環境因子
- 個人因子
といった5つの要素で構成されています。
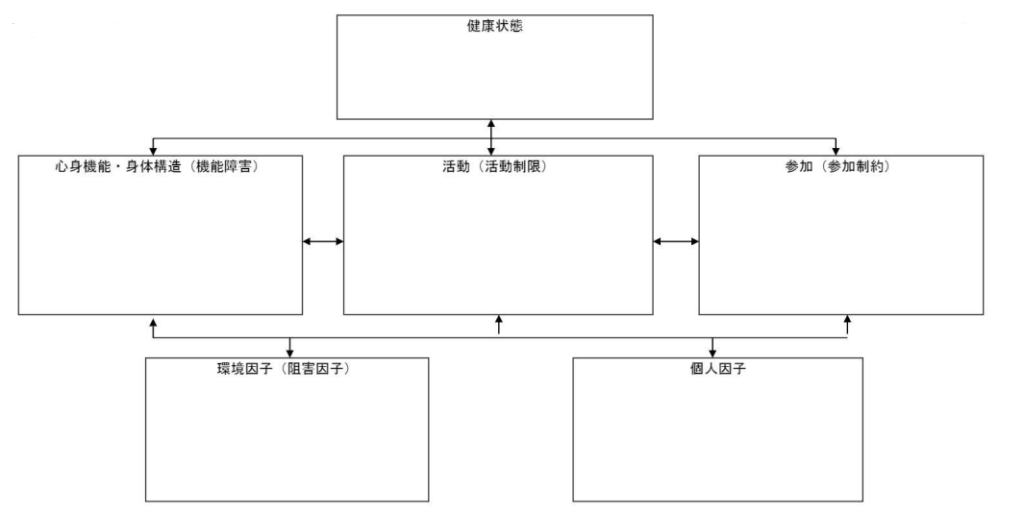
図で整理して視覚化することによって、問題点や介入のポイントを明確にすることができます。
項目⑧:統合と解釈
「統合と解釈」とは、
- 面接で聞き取った患者さんの訴え
- 観察で明らかになったADL動作の問題点
- 作業療法評価の結果
といった情報を結び付けて、その後の目標設定やプログラム立案を行う過程のことです。
最も重要な過程の1つであり、実習中に1番時間と労力をかけて取り組む部分でもあります。
項目⑨:目標設定、治療計画立案
目標設定をする際は、
- 長期目標・・希望に限りなく近いもの
- 中期目標・・退院日に達成できるもの
- 短期目標・・確実に達成できるもの
といったように、細かく分けて設定することがとても大切です。
短期目標が達成できてないのに中期・長期目標が達成できることはありません。
しっかりとした目標が立てば、おのずと治療プログラムも具体的なものとなるはずです。
項目⑩:治療経過(中期評価、最終評価)
治療プログラムを行った場合、結果の振り返りを行いましょう。
具体的には、
- 患者さんの変化(心理面・身体面)
- セラピストの関わり方の変化
- 患者さんとセラピストとの関係性の変化
といったように、自分が介入を行ったことで生じた事実を客観的に記載します。
項目⑪:考察、まとめ
ここでは、治療プログラムやその結果に対し、検討した自分の意見について記載します。
介入の根拠を示すために、参考文献をいくつか示すことも大切です。
まとめの際は、結語は未来に向けての課題などを書いても構いません。
項目⑫:参考文献
レポートのさいごに、参考文献を記載しておきましょう。
治療計画の見直しや考察を行う上で、根拠となる情報源を示すことでレポートの信用性が高まります。
いつか見直す時にも役立つので、その都度まとめておくと便利です。
まとめ:作業療法臨床実習レポートの書き方について
以上、「作業療法臨床実習レポートの書き方」でした。
さいごにもう一度おさらいしておきましょう。
レポートに記載すべき項目まとめ
- はじめに(タイトル+要約文)
- 症例プロフィール
- 医学的情報
- 社会的情報
- 他部門からの情報
- 作業療法評価
- ICFによる整理
- 統合と解釈
- 目標設定、治療計画立案
- 治療経過(中期評価、最終評価)
- 考察、まとめ
- 参考文献
少しでも効率よく実習を進められるよう、ぜひ本記事を参考にしていただければ幸いです。
また以下の記事では、レポート作成に役立つ「SOAP」という手法について解説しています↓↓