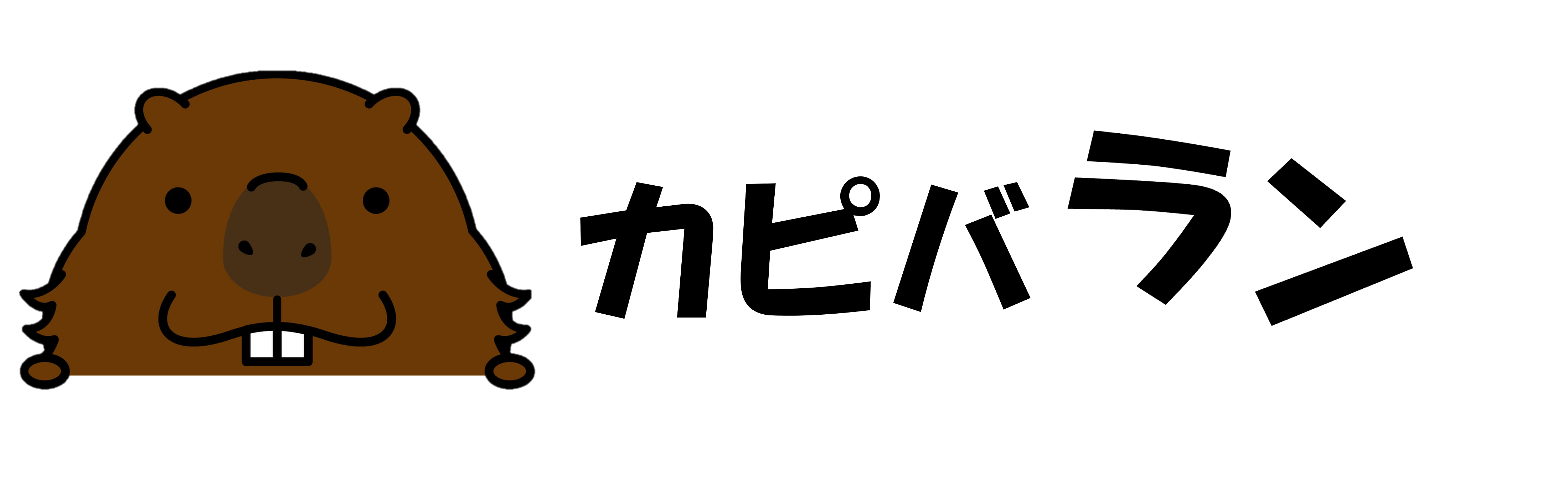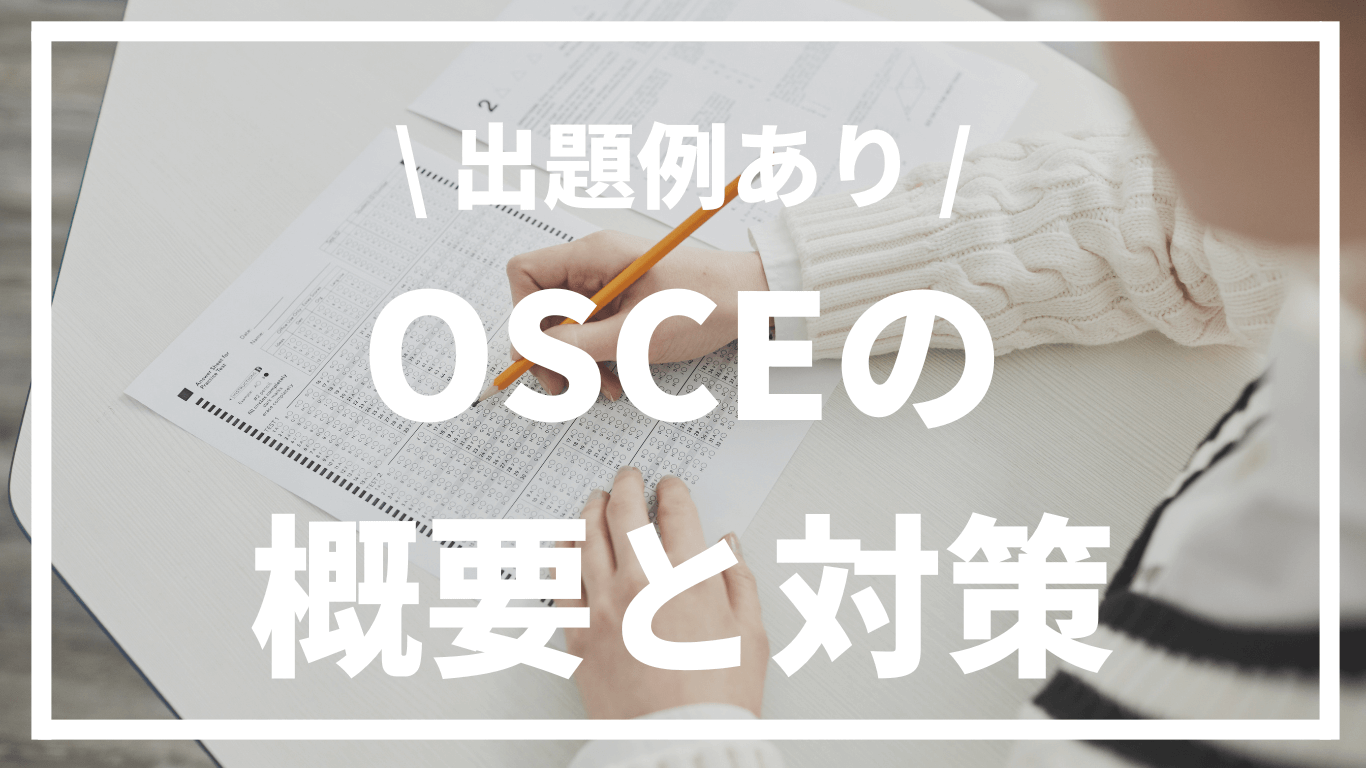N君
N君臨床実習の前にもうひとつ、OSCE(オスキー)って試験があるんだけど、これってどんな試験なの?試験の概要やポイントについて教えてほしいなぁ。
こうした疑問に答えます。
臨床実習へ出かける前の最後の試験が、「客観的臨床能力試験(OSCE)」です。
どちらの学校でも実施されている試験なので、
- OSCEってどんな試験?
- どんなことを勉強すべき?
- 実際の試験内容は?
このように疑問・不安を感じている方も多いかと思います。
今回は、「客観的臨床能力試験(OSCE:オスキー)」について、概要や試験対策のポイントについて解説します。
本記事を一通り読めば、試験の概要について十分理解でき、自信をもって臨めるはずです。
これから試験を控えてる方は、ぜひ参考にしてください!
客観的臨床能力試験(OSCE)ってどんな試験?

「OSCE」とは、「Objective Structured Clinical Examination:客観的臨床能力試験」の略称です。
主に、臨床場面を想定した模擬患者を相手に問診や検査などを行い、対応の仕方や手技の確認を行います。
OSCEについては、以下のようにまとめられています。
 N君
N君合格しないと実習には行けない・・実習前の最後の試練だね。
主な実施時期
作業療法学科のOSCEの実施時期は、概ね2月ごろに実施されます。
スケジュールとしては比較的余裕があるので、年を越してから準備をはじめるくらいで問題ありません。
OSCEで指摘されたことを、4月からの実習に向けて復習していきます。
学ぶべき4つのポイント

作業療法学科のOSCEで学ぶべきポイントは、以下の4つです。
- 与えられた資料から、症状について検討する
- 検査、測定を行う難しさを知る
- 結果のまとめ方、報告の仕方を知る
- 対象者の方への接し方を知る
先ほども少し書きましたが、OSCEは臨床実習を行う臨床能力を身につけているかを試す実技試験です。
試験を通して、この4つのポイントについて学んでいきます。
ポイント①:与えられた資料から、症状について検討する
OSCEではあらかじめ資料が渡され、以下のような情報がまとめられています。
- 一般情報(年齢、家族構成、職業歴など)
- 医学的情報(診断名、現病歴、既往歴など)
- 他部門からの情報(Dr、NS、PTなど)
- 評価結果(主観的・客観的)
これらは基本的に、すべてカルテに記載されている情報です。
ここから対象者の方の状態を予測し、どのような評価・測定を行うか判断します。
注意:相手ができないことを指示しない
ここで注意が必要なのが、「相手ができないことを指示しない」ということです。
与えられた対象者の方の情報を、読み違えないように気をつけましょう。
指示の仕方のNG例は、以下のとおりです。
- 自力で立てない人に、「○○まで移動して」と指示する
- 寝返りできない人に、「向きを変えて」と指示する
- 自力で座れない方に、介助なしで動作を指示する
安全にリハビリを行う上では、事前にリスクを把握し、適切に対処することが大切です。
OSCEを通して、こうした視点を持って対象者の方と関わることの大切さを学びましょう。
ポイント②:検査・測定を行う難しさを知る
 N君
N君実技の授業は今まで何度もあったし、今さら注意することなんてあるの?
OSCEは、模擬患者を相手に行うため、これまでの学生同士でやった授業とはまるで雰囲気が違います。
臨床さながらの緊張感があるので、改めて検査・測定を行う難しさを経験することができます。
実技試験で多くの方が体感することになると思いますが、
- 思ったように物事が伝えられない
- 相手の身体をうまく動かせない
- 検査内容をど忘れしてしまう
- 緊張で手足が震える
これらは、臨床実習に向けて自身の成長につながる貴重な経験です。
試験が思ったようにできなかったからといって、落ち込む必要はまったくありません。
OSCEでの反省点を臨床実習に十二分に活かせるよう、自己学習の糧としていきましょう。
ポイント③:結果のまとめ方、報告の仕方を知る
OSCEでは、一通りの検査・測定を行って終わりというわけではありません。
試験では、例として以下のように出題されます。
 カピまる
カピまる○と△について評価してください。
 カピまる
カピまる評価結果から、この方のトイレ動作における
問題点について説明してください。
このように、検査・評価した結果得られた情報を、その場でまとめ、報告することが求められます。
臨床場面でも、このようにコミュニケーションを取る機会はとても多いです。
結果をまとめ、報告する力を身につけておくことは、実習中に円滑なコミュニケーションを取ることに繋がります。
ポイント④:対象者の方への接し方を知る
OSCEでは基本的に、試験の様子をビデオで撮影します。
試験後には自己学習として、自分や他者の言動についてお互いにフィードバックを行います。
検査・測定手技の正誤だけではなく、
- ことば遣い
- 口調、声のトーン
- 視線の送り方
- 身振り手振りの仕方
といった、自分では気付きにくい、自分の姿を客観的に見ることができます。
OSCEは、自分自身の良い点・悪い点に気付くための良いきっかけですので、ぜひ活用しましょう。
参考:OSCEの実際の出題例

次に、OSCEの出題例をご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
一般情報
- 70代男性(女性)、165(155)cm、70(60)kg
- 家族構成:長男、孫と3人暮らし
- キーパーソン:長男
- 家屋状況:一戸建て
- 職業歴:事務職、定年後は無職
- 経済状況:年金
- 趣味:ウォーキング
- ニード:自立歩行、ADL自立
医学的情報
- 診断名:脳内出血(右前頭頭頂葉皮質下)
- 障害名:左片麻痺
- 現病歴:X日・・飲酒後就寝、左半身脱力、A市立病院受診。CTにて脳出血認める。家族の希望で当院転院。X+1日・・開頭血腫除去術を行う。
- 既往歴:X-2Y日・・ポリープにて精査入院。腰痛あり
- 服薬状況:アテレック、タナトリル、ムコスタ
他部門からの情報
- NS:ADLは、術後X+7のため食事動作以外全介助。コミュニケーション◎
- PT:X+2日開始。病室にてROMex、座位保持exを実施。目標:自立歩行。
評価結果
- 第一印象:左側を向かず表情の変化もほとんどない。リハビリは消極的。
- 面接場面
- 初期における主訴・・頭痛、腰痛、睡眠不足
- 基本動作自立、自立歩行、在宅復帰を希望
- 自ら神経質な性格と述べ、職員への不満を口にすることが多い
- リハスタッフには好意的で、気遣いを示すこともある
| 評価項目 | 初期評価(X+7~14日) |
|---|---|
| 意識 | JCSレベル1 |
| バイタルサイン | 血圧:145/100mHg 脈拍:50~65/分 |
| 腱反射 | 麻痺側亢進 |
| 病的反射 | バビンスキー反射:陰性 ホフマン反射:陽性 トレムナー反射:陽性 |
| 筋緊張(臥位) | 安静時・他動時ともに、 ・麻痺側上肢 ・肩甲骨周囲筋 ・体幹 ・下肢 で低緊張となる |
| 感覚(麻痺側) | 表在:左上下肢中等度~軽度鈍麻 深部:上肢・・感覚脱失 下肢・・中等度鈍麻 |
| バランス機能 | 座位:左右とも頸部・体幹立ち直り〇 |
| ブルンストローム | 麻痺側上下肢、手指ともにⅡ |
| 握力 | 非麻痺側:25kg |
| ピンチ力 | 非麻痺側 ・指腹つまみ・・3kg ・側腹つまみ・・4kg |
| MMT | 非麻痺側:未実施 観察より5程度と判定 |
| 高次脳機能 | 線分抹消テスト、図形模写 →半側空間無視、注意障害の疑いあり |
| 心理面 | プライド、向上心あり。 自尊心が傷つき葛藤している |
| 痛覚 | 頭痛、腰痛 |
- 基本動作
| 評価項目 | 初期評価(X+7~14日) |
|---|---|
| 寝返り | 非麻痺側への寝返り :介助頸部を右上部へ挙上するが、 骨盤・体幹の回旋不可。 |
| 起き上がり | 臥位→座位 :介助 介助で側臥位:on elbowへ姿勢変換✖ 座位→臥位 :介助にて側臥位、下肢の挙上✖ |
| 立ち上がり | つかまり立ちするが、麻痺側へ倒れそうになる |
| 端坐位 | 後方または麻痺側へ傾く |
| 立位 | 非麻痺側でベッド柵につかまるが、体幹が後方へ 側屈しやすく、非麻痺側で支持 |
- ADL(FIM:66点 / 126点)
| 食事 | セッティングにて自立 食べこぼしはあるが、食べ残しはない |
| 整容 | セッティングにて自立 |
| 更衣 | 上衣・下衣ともに介助 |
| トイレ動作 | 尿便使用。摘便 |
| 入浴 | 未実施 |
| 移乗 | 介助 |
| 移動 | 介助 |
| その他 | コミュニケーション問題なし 痛み、睡眠不足を理由にリハビリを休む →易疲労性が伺える 指示を聞かずに無関係なことを話し出す →集中・注意力低下が伺える |
 N君
N君データばっかり沢山だなぁ・・
ここから患者さんの姿を想像するのか。
上記のように、具体的な設問などは与えられません。データから患者さんの姿を想像する必要があります。
考えるポイントはどんなところ?
与えられた情報にあるように、この方は「ADLの自立」「在宅復帰」を目標としています。
そのためまずは、日常生活を送るうえでの問題点を整理し、それに向けたアプローチを行う必要があります。
問題点の整理
日常生活の具体例として、
- トイレ動作
- 更衣動作
- 食事動作
- 入浴、清拭
といった場面における問題点について整理します。
評価の実施
上記の問題点を整理するために必要な評価として、以下のものが挙げられます。
- 感覚検査(表在、深部)
- 腱反射
- 座位からの立ち上がり動作
- 認知機能
- バランス機能
- 関節可動域
- リーチ動作
- 家屋評価
やみくもに検査を行うのではなく、目的に合ったものをピックアップして行うことが大切です。
必要な検査のみ実施することは、時間短縮はもちろん、対象者の方の負担軽減にもつながります。
予想される出題テーマ
上記のことをふまえ、今回出際されそうなテーマはこちらです。
必要となる検査・評価も多いことから、さまざまな角度から問題が出題されることが予想されます。
事前に与えられたデータをしっかりと読み込み、患者さんの姿を具体的に思い浮かべましょう。
まとめ:【作業療法学生向け】OSCEへの対策方法
以上、「客観的臨床能力試験(OSCE:オスキー)」について、概要や試験対策のポイントについて解説しました。
実習前の最後の試練ですが、客観的に自分を見つめ直すチャンスでもあります。
本記事で紹介したポイントを心にとめて、学びのある試験を迎えてください。
以下の記事では、各種評価について分かりやすく解説していますので、ぜひ復習にご活用ください。
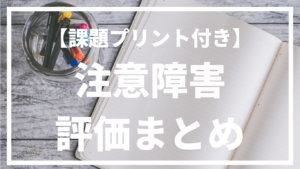
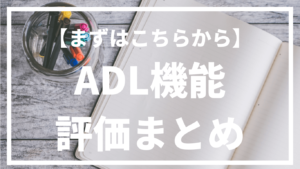
今回は以上です。最後までご覧いただき、ありがとうございました。