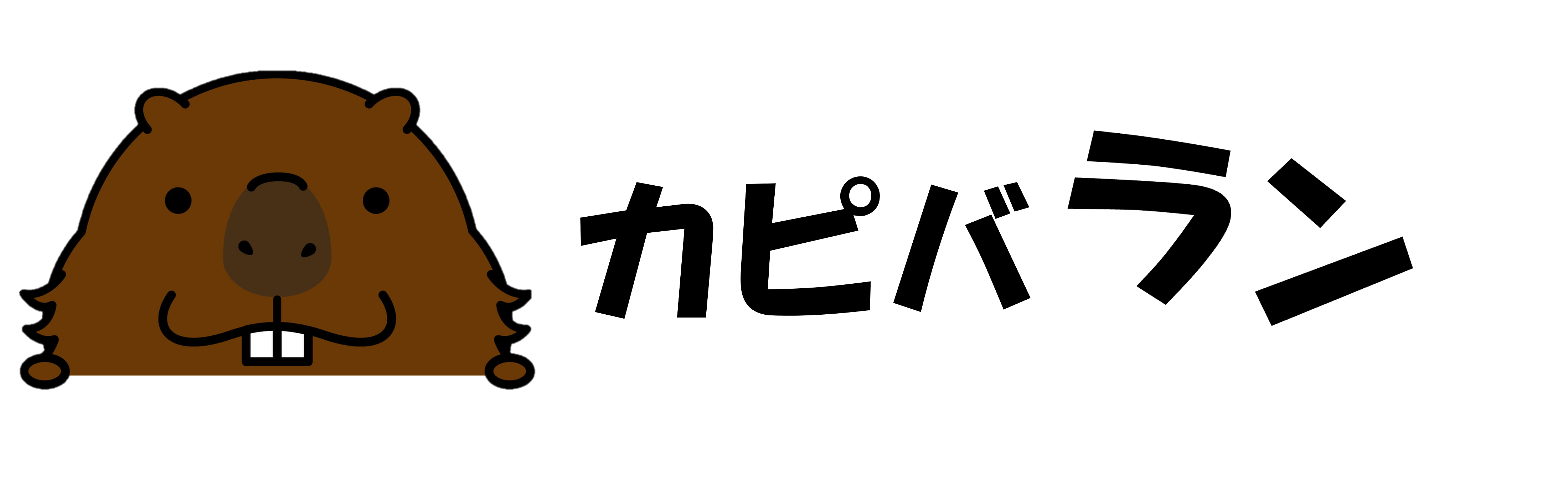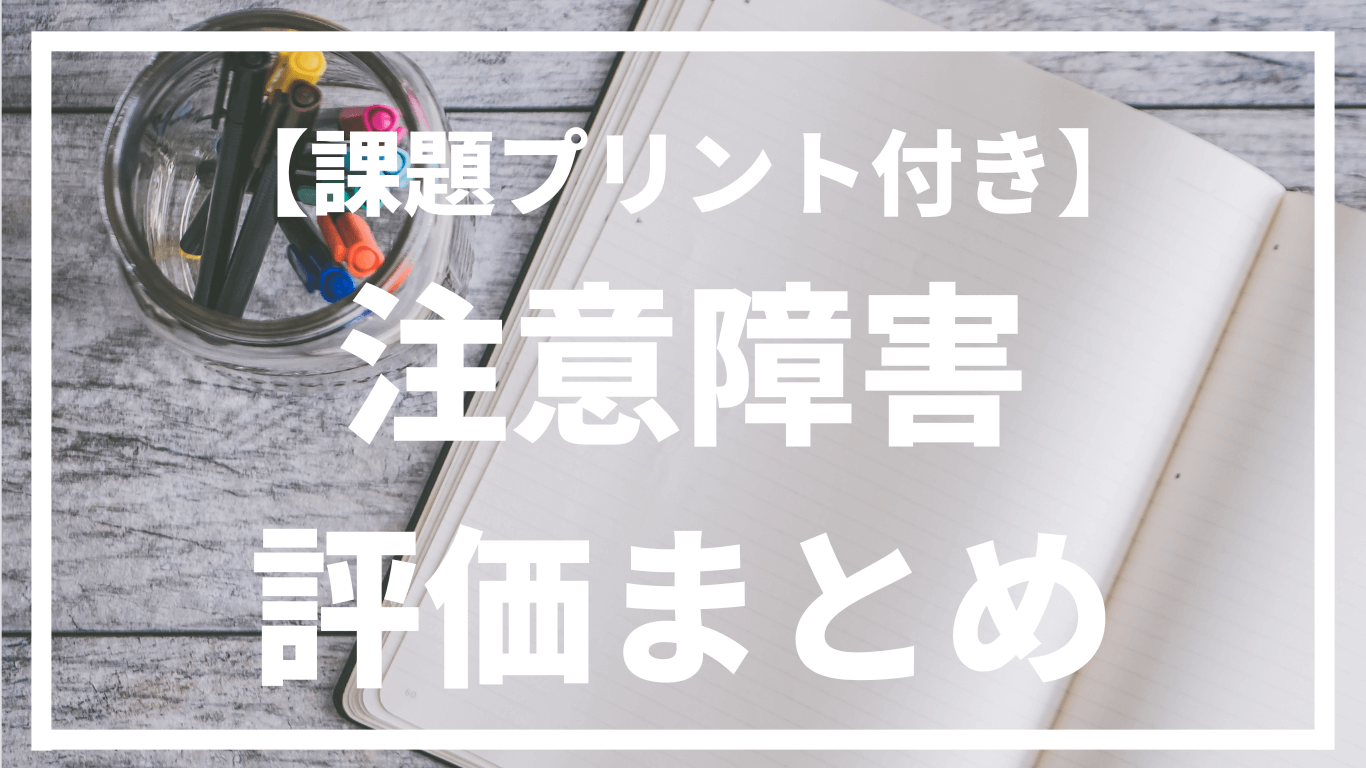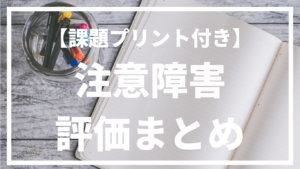N君
N君注意障害について勉強したいなぁ。
 カピまる
カピまる概要から具体的な評価方法まで、くわしくまとめていくよ!
- 作業中にミスしやすくなる
- 同時に複数の仕事をこなせない
- 集中力が続かない
注意障害では、こうした症状が見られるといった特徴があります。
本人が抱える症状を理解するうえで、評価を適切に実施することはとても大切なことです。
本記事では、注意障害の概要をはじめとして、具体的な評価方法について解説していきます。
またリハビリ場面で使用できる課題プリントについて、併せてご紹介していきます。
注意障害についてこれから学ぶ方だけでなく、現場で働く方も必見の内容となっています。
- 注意機能の概要について復習したい!
- 注意障害に対する評価方法を知りたい!
- リハビリで使える課題プリントが欲しい!
上記に該当する方は、ぜひ最後までご覧いただき、参考にしてみてください!

ブロックエディターに完全対応!
直感的な操作で簡単ブログ作成!
見るたび気分が上がるデザイン!
圧倒的な使い心地の最強テーマ!
圧倒的な使いやすさ、どんどん追加される新機能、おしゃれなデザイン性
そのすべてを兼ね備えた最強のWordPressテーマ「SWELL」
\ 国内最高峰の使い心地を手に入れよう /
注意機能の概要まとめ

注意障害についてお話しする前に、注意機能の概要についてまとめます。
そもそも「注意」とは?
「注意」とは、まとめると以下のような機能です。
つまり、対象に意識を集中させ、持続させる機能を意味します。
「注意」≒「集中力」と置き換えると、理解しやすいかもしれません。
- 長い時間集中することができない
- 見落とし、ミスが多い
こうした状態は、ある種の「注意(≒集中力)が低下した状態」と言えます。
主な分類方法
注意機能は、一般的に
- 全般性注意機能
- 空間性注意機能
の2つに分類されています。
全般性注意機能
全般性注意機能は、その名のとおり注意機能全般のことを意味しており、さらに以下のように分類されます。
| 段階 | 機能 |
|---|---|
| 注意の焦点化(感度) | 特定の感覚刺激に反応する機能 |
| 注意の維持(持続性) | 連続あるいは繰り返して一貫した反応を行う機能 |
| 選択的注意(選択性) | 干渉刺激がある場合に、行動や注意を維持できる機能 |
| 注意の切り替え(転換性) | 異なる課題間で、注意を移動できる機能 |
| 注意の分割(配分性) | 複数の課題に並行して対応できる機能 |
これら5つの機能は階層性を有し、下位の注意機能が上位の注意機能の基礎となります。
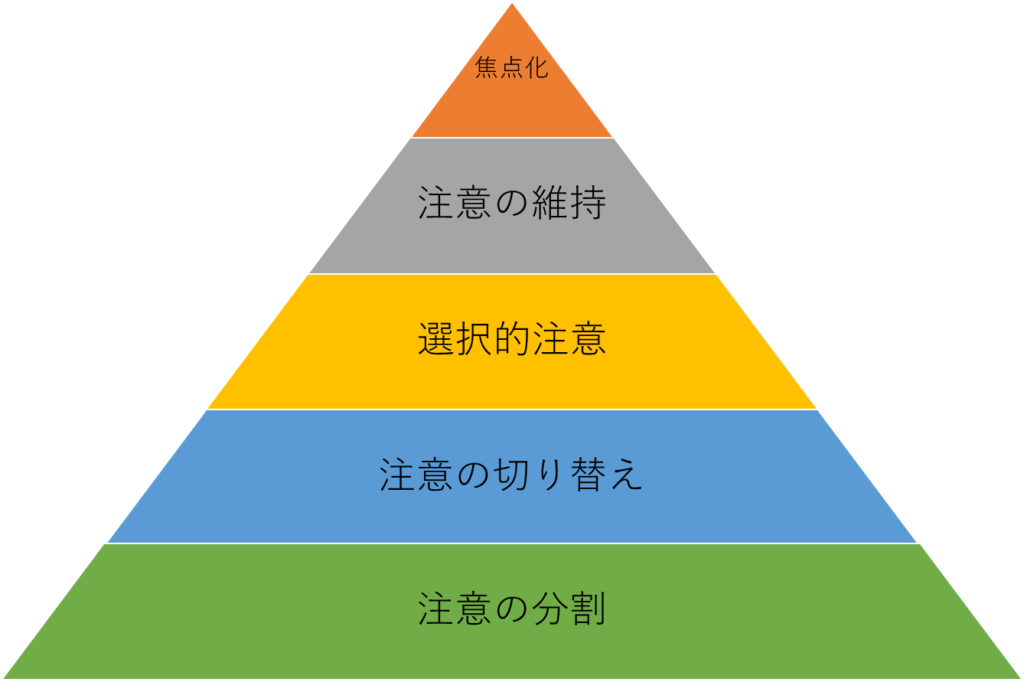
空間性注意機能
空間性注意機能とは、外界と自分との空間的関係における注意のことです。
視覚(認知)と運動(反応)と密接に関わっているとされています。
注意障害の基礎知識

次に、注意障害の概要について解説していきます。
「注意障害」の定義
注意障害とは、日常生活場面で必要とされる注意機能が低下した状態のことです。
先ほど注意機能は、
- 全般性注意機能
- 空間性注意機能
の2つに分類されると述べましたが、注意障害はこのうち全般性注意機能の障害を意味します。
主な4つの分類
注意障害は、主に以下の4つに分類されます。
- 持続性注意の障害
- 選択性注意の障害
- 転換性注意の障害
- 配分性注意の障害
それぞれの概要と、障害の例についてご紹介します。
持続性注意の障害
持続性注意が障害されると、集中力が続かないといった症状が見られます。
単純な課題であっても長時間続けられず、別のことに意識が向いてしまったりします。
- 単純な課題を続けられない
- 時間が経つにつれて見落としや誤りが増える
- 途中で眠くなってしまう
選択性注意の障害
選択性注意は、しばしば「カクテルパーティー効果」とも呼ばれます。
これは、立食パーティーで騒がしい状況の中でも、特定の人達の会話に耳を澄ませ、それを聞き取ることが出来る機能を意味します。
選択性注意が障害されると、ターゲットとする刺激と外部からの干渉刺激との区別が困難になり、注意が散漫になってしまいます。
- 騒がしい中だと、会話に集中できない
- お店にある商品の中から、特定の物が見つけられない
- 外で待ち合わせをすると、友人を見つけられない
転換性注意の障害
転換性注意とは、特定の課題に向けて注意を維持している状態でも、周囲に対しても意識を向け、場合によっては注意の対象を変更する機能のことです。
障害された場合、こうした注意の切り替えが困難になる症状が見られます。
また反対に、過剰に注意が転換してしまう症状が出現することもあります。
- 1つの課題に集中し、他の課題が手付かずになる
- まわりに意識が向かず、自己中心的な行動を取る
- まわりが気になり、注意が散漫になる
配分性注意の障害
配分性注意が障害されると、複数の刺激に対して同時に注意を向けられなくなります。
1つの課題や検査では問題が無くても、2つの課題や検査を行った際に、配分性注意の障害が発見されることがあります。
- 一度に複数の品物の調理が行えない
- 自動車を運転している際に、周囲の状況に意識を向けられない
- 電話をしながら、メモを取ることができない
注意障害に対する4つのアプローチ

注意障害に対するアプローチ方法には、以下の4つがあります。
- 全般的アプローチ
- 特異的アプローチ
- 動作課題
- 環境調整
注意障害では、
- 作業中にミスしやすくなる
- 同時に複数の仕事をこなせない
- 集中力が続かない
といった症状がみられ、日常生活を送るうえで大きな影響を及ぼします。
自立した生活を送れるよう支援を行うためには、注意障害に対する適切なアプローチ方法を知ることが大切です。
作業療法を行う上での大原則
注意障害に対してアプローチを行う上で、以下の点は必ず押さえておきましょう。
- しっかりと覚醒した状態のときにリハビリを行う
- 課題の難易度は、低いもの→高いものの順に行う
- 結果に対するフィードバックを適宜行う
しっかりと覚醒した状態のときにリハビリを行う
十分に覚醒していない場合、
- 課題に集中できない
- 過度に疲労を感じてしまう
といった状態に陥る可能性が高くなります。
 N君
N君眠たい時や疲れている時だよね!
確かに集中しろと言われても難しいよ…。
何よりもまず初めに、課題を実施できる状態であるかどうか確認するようにしましょう。
課題の難易度は、低いもの⇒高いものの順に行う
課題を実施する順番にも、注意が必要です。
- 簡単すぎる問題が続く場合
- 難しすぎる問題が続く場合
こうした課題では、その方の機能を適切に評価することができません。
少しずつ難易度を上げていくことで、集中力を長時間保つことが可能となり、正しく評価することができます。
難しい課題ばかりくり返し行ってしまうと、
 カピまる
カピまる全然できなかった…自分はなんてダメな人間なんだろう…
このように、自己肯定感の低下にもつながってしまう恐れもあるため、気をつけましょう。
結果に対するフィードバックを適宜行う
- 間違いが何問も続いてしまっている場合
- 表情などに不安そうな感情が表れている場合
こうした時には、現在の状態を伝え、正しく修正することを促す必要があります。
声掛けによって一区切りしながら行った方が、高い集中力を保つことができるので、課題成績も良くなります。
 カピまる
カピまるフィードバックのし過ぎはNG!適切なタイミングで行うことが大切なんだ!
以下の記事では、それぞれの具体的なアプローチ方法について、くわしく解説しています。
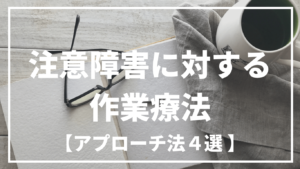
主な評価方法
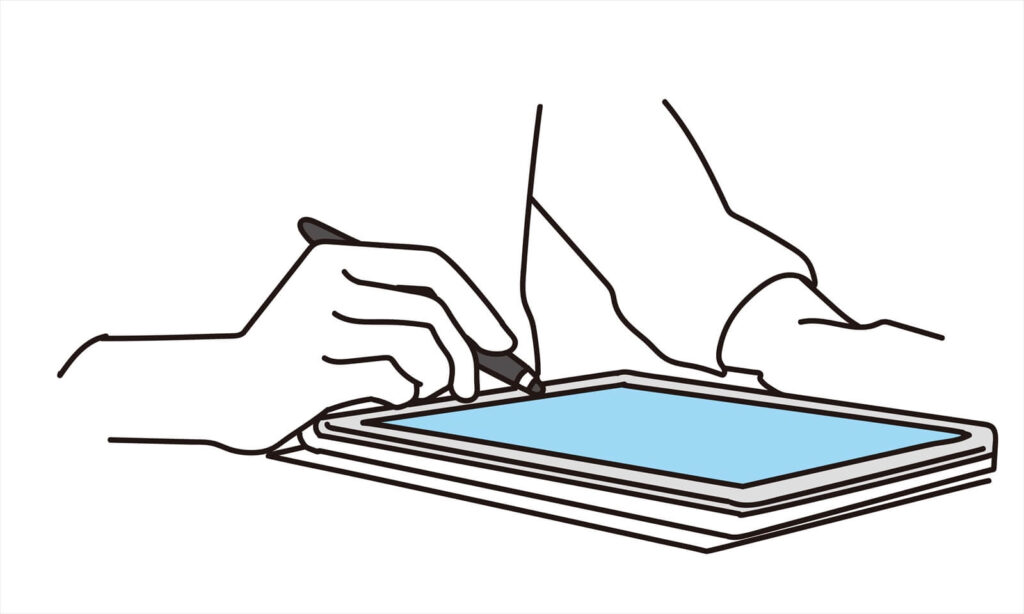
- 持続性注意
- 選択性注意
- 転換性注意
- 配分性注意
という4つの注意機能に対する総合的な評価スケールとして、「標準注意検査法(CAT )」が一般的に使用されています。
標準注意検査法(CAT)の概要
標準注意検査法(CAT)の評価できる機能は、以下のとおりです。
- 注意の容量
- 持続性
- 選択
- 転換(変換)
- 配分
またこちらの検査は、以下7つの下位項目から構成されています。
- Span(視覚性、聴覚性)
- 末梢課題(視覚性、聴覚性)
- SDMT( Symbol Digit Modalities )
- Memory Updating Test
- PASAT( Paced Auditory Serial Addition Test )
- Position Stroop Test
- CPT( Continuous Performance Test )
CATの概要については、以下の記事でくわしく解説していますので、あわせてご覧ください。
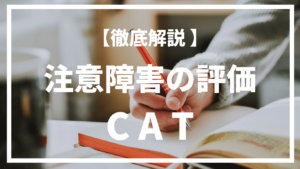
参考:その他評価スケールについて

注意障害に対するその他の評価スケールには、以下のようなものがあります。
| 注意機能 | 評価スケール |
|---|---|
| 持続性注意 | ・CPT( Continuous Performance Test ) ・PASAT( Paced Auditory Serial Addition Test ) ・Trail Making Test ( Part A, B ) ・末梢課題(文字、記号等) |
| 選択性注意 | ・仮名拾いテスト ・AMM( Audio-Motor Method ) ・Stroop Test ・上中下テスト ・PASAT ・Trail Making Test ・末梢試験 |
| 転換性注意 | ・Trail Making Test( Part A, B ) ・SDMT( Symbol Digit Modalities Test ) ・Memory Updating Test |
| 配分性注意 | 2つの注意課題を同時に実施することで評価する ( ex. PASATとTrail Making Test Bを実施する ) |
本記事では、その中でも以下の評価スケールについて、詳しくまとめていきます。
- Span(視覚性、聴覚性)
- 末梢課題(視覚性、聴覚性)
- SDMT( Symbol Digit Modalities )
- Memory Updating Test
- PASAT( Paced Auditory Serial Addition Test )
- Position Stroop Test
- CPT( Continuous Performance Test )
評価の説明にあわせて、すぐに使える課題プリントもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
①:Span(視覚性・聴覚性)
Span(視覚性、聴覚性)では、
- 作動記憶
- 短期記憶
- ワーキングメモリー
といった機能について評価を行います。
この評価スケールは、「Digit Span(数唱)」「Tapping Span(視覚性スパン)」という2つの課題で構成されます。
検査の実施方法について
この検査では、
- 順唱(forword)
- 逆唱(backword)
という2つの方法によって評価を行います。
順唱(forword)
| 〇もしくは✖ | 第1系列 | 〇もしくは✖ | 第2系列 |
|---|---|---|---|
| 2-5 | 5-4 | ||
| 1-8-3 | 4-9-7 | ||
| 4-2-6-1 | 1-6-3-8 | ||
| 9-5-1-8-2 | 7-3-9-4-2 | ||
| 7-3-9-1-4-6 | 6-1-2-5-7-9 | ||
| 9-5-2-7-1-3-4 | 1-3-7-2-8-4-6 | ||
| 3-6-7-9-1-8-4-5 | 9-6-7-2-5-1-3-8 | ||
| 7-4-5-9-3-8-1-6-2 | 5-3-4-9-7-1-6-8-2 |
逆唱(backword)
| 〇もしくは✖ | 第1系列 | 〇もしくは✖ | 第2系列 |
|---|---|---|---|
| 9-2 | 6-1 | ||
| 3-7-4 | 1-5-8 | ||
| 2-8-6-1 | 4-9-2-7 | ||
| 4-1-9-2-5 | 3-7-5-2-6 | ||
| 2-1-5-8-9-3 | 8-4-2-9-6-3 | ||
| 8-6-3-1-2-7-9 | 6-9-1-7-5-8-4 | ||
| 3-8-2-7-6-9-4-1 | 7-5-2-8-4-3-1-9 | ||
| 6-3-5-7-1-2-4-9-8 | 2-9-7-3-1-6-4-8-5 |
実施方法については、以下の手順を参考にしてください。
- まず第1系列の数字を1つ1秒の早さで読み上げる。
- その直後に順唱(そのままの順番)での反応を確認する。
- 正答の場合は次の系列に進み、間違えた場合は第二系列を行う。
- 同じ桁の2系列で不正解の場合、検査を中止する。
- 聞き返しがあった場合、再度説明は行わない。
- 注意して聞くように促してから、第2系列に移る。
繰り返し説明を行わない点については、正確に検査を行う上でとても重要ですので、押さえておきましょう。
②:PASAT( Paced Auditory Serial Addition Test )
PASATでは、配分性注意機能について評価を行います。
といったように次々と読み上げられる数字と、1つ前の数字を足していく課題です。
数字を読み上げる間隔によって、「2秒条件」「1秒条件」が設定されています。
60個のうち、いくつ正解したかによって評価します。
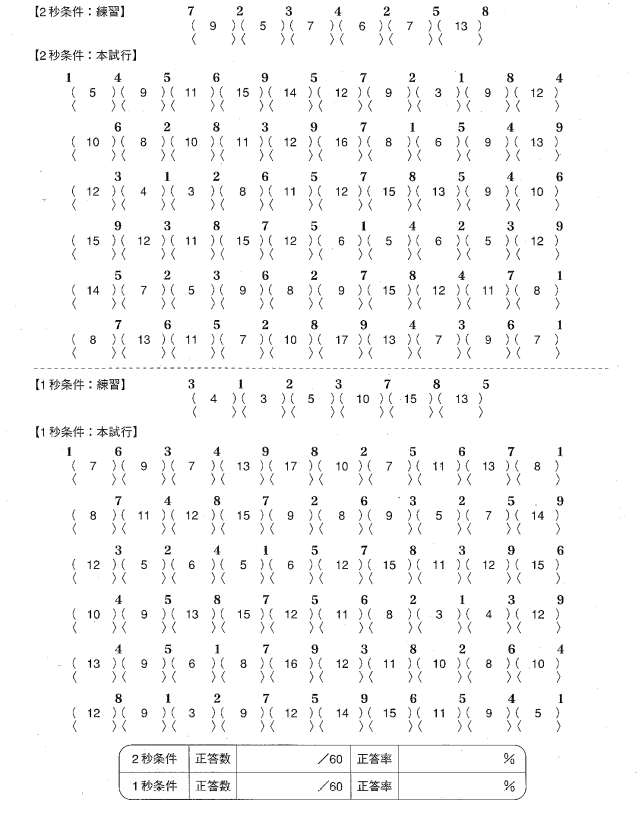
③:Trail Making Test ( Part A, B )
TMTとは、トレイルメイキングテスト(Trail Making Test)の略称です。
- TMT-A
- TMT-B
という2種類の検査から構成されており、
- 視空間認知機能
- 目と手の協調性
- 視野や視力
- 情報処理能力
- 各種注意機能(持続性・選択性・転換性・配分性)
- ワーキングメモリー
といった、さまざまな注意に関連する機能について評価することができます。
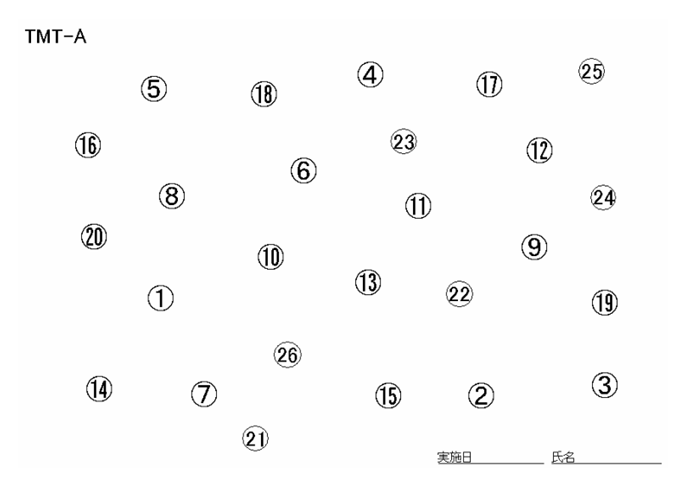
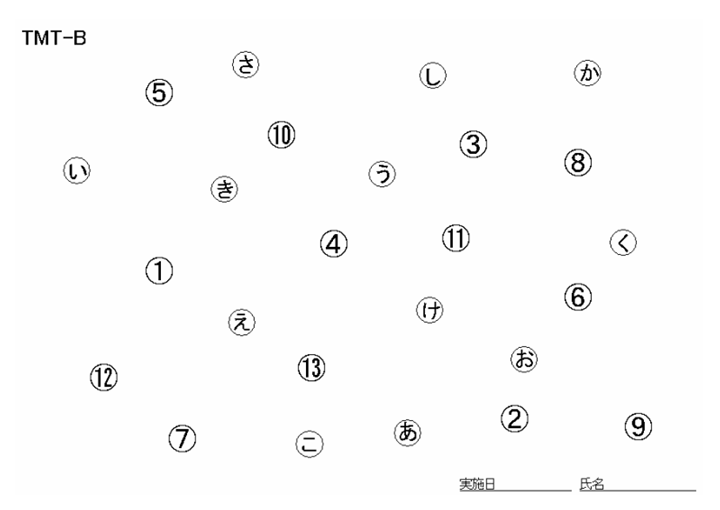
詳細については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
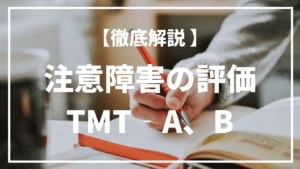
④:末梢課題(文字、記号等)
抹消課題では、選択性注意注意機能について評価を行います。
- 視覚性抹消課題(Visual Cancelling Test )
- 聴覚性検出課題(Auditory Detection Test)
という2つの検査で構成され、「数字」「図形」「仮名」の3つのパターンを使用します。
指定された数字・図形・仮名を見つけ、〇で囲ったり線を引くことによって、早く・正確に抹消していきます。
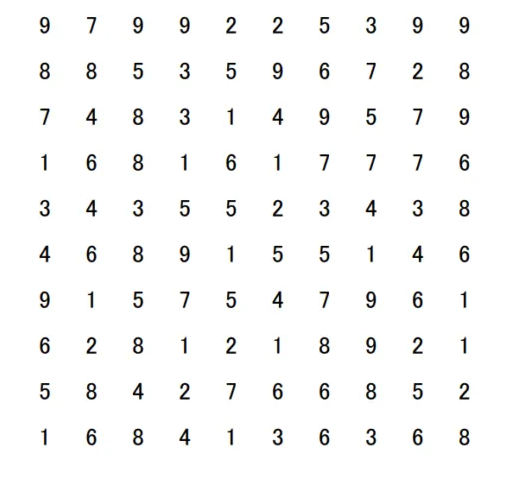
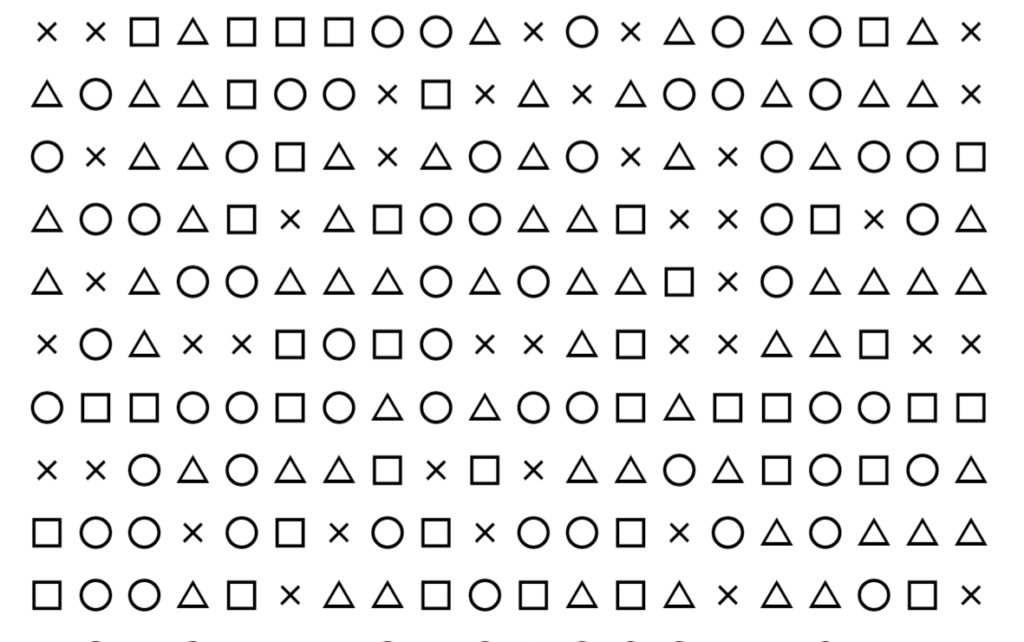
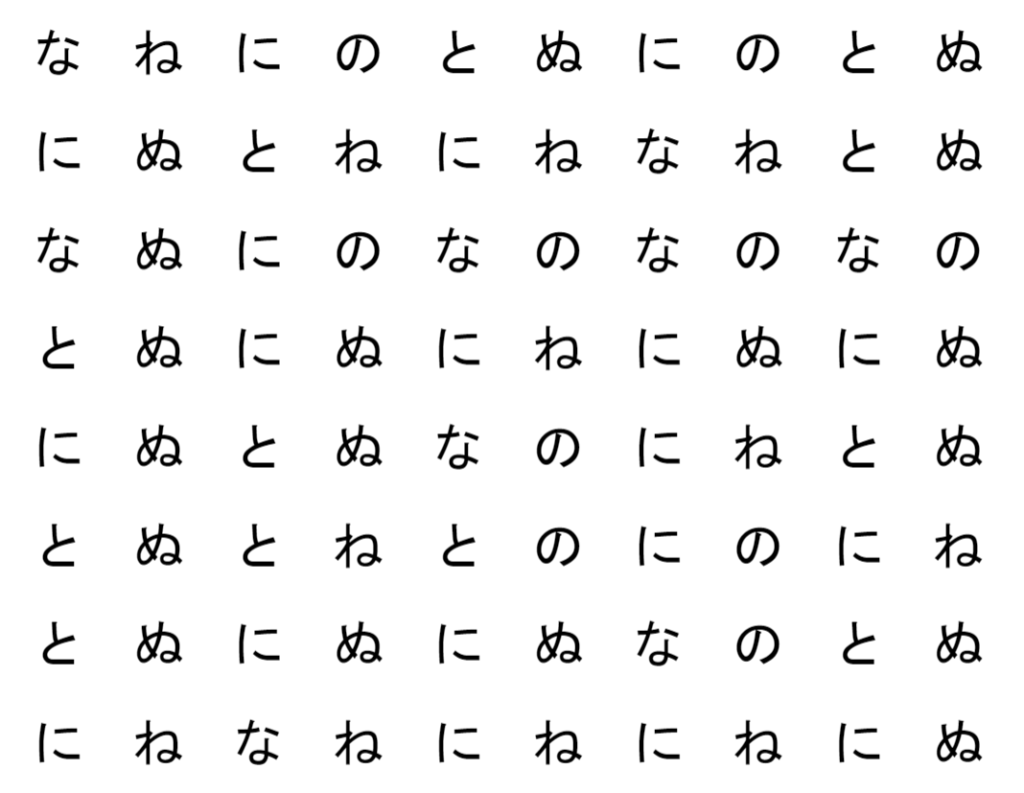
⑤:仮名拾いテスト
仮名拾いテストは、選択性注意機能について評価を行います。
この検査は、ひらがなで書かれた文章から「あ・い・う・え・お」に〇をつける課題です。
2分間で正しく〇をつけられた数で評価します。
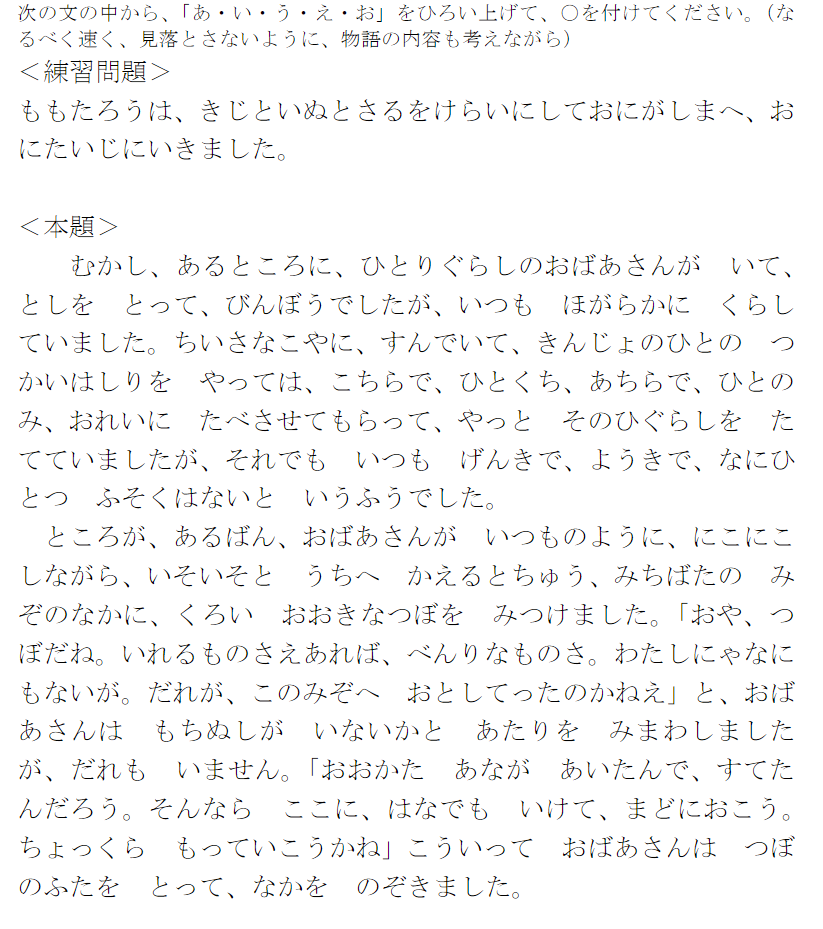
⑥:Position Stroop Test (上中下テスト)
Position Stroop Testでは、転換性注意機能について評価を行います。
検査では、「上」「中」「下」という漢字が書かれている位置について回答します。
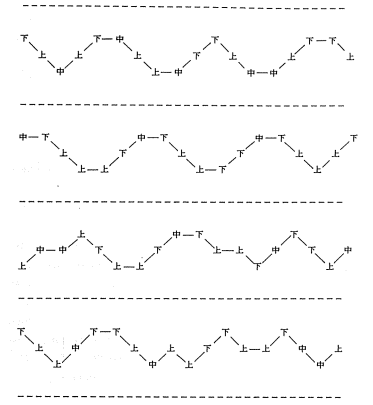
画像の問題(上段)では、「上、中、下、中、上、上、中、下・・・・」となります。
※文字の音読ではなく、その字が書かれている「位置」を答える点に注意しましょう。
さいごに
本記事では、注意障害の概要をはじめとして、具体的な評価方法について解説しました。
- 作業中にミスしやすくなる
- 同時に複数の仕事をこなせない
- 集中力が続かない
といった症状に対して理解するうえで、正しい知識をもって評価することはとても重要です。
具体的なアプローチ方法や課題プリントを参考に、今後の生活にぜひ活用してください!
今回は以上です。最後までご覧いただき、ありがとうございました。